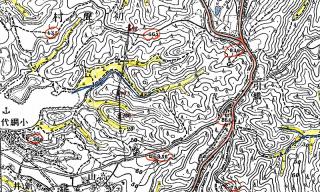7月 18th, 2019
うたの位相 その2
日本語で書かれた「戦争文学の最高峰」などというものがあるとすれば、吉田満の『戦艦大和ノ最期』をあげるのが、まずは順当かも知れない。
特攻出撃して被弾沈没する巨艦のむなしさ、戦闘の実際を語って圧巻である。しかしそれも戦争の一側面にすぎず、むしろその最奥部に届いているとは言えないのである。
先の大戦での「日本側」死者約310万人(内閣衆質152第15号、2001年8月28日)のうち、「戦死」の多くは、実は餓死と戦病死であって(金子兜太『あの夏、兵士だった私』ほか)、とりわけ「外地」における極限状況は日本兵の一部をして人肉食の餓鬼に変ぜしめた(大岡昇平『野火』ほか)。しかし、アジア大陸に「進出」した「皇軍」が殺戮し、また占領した地域での死者の数は、「日本側」とは桁違いに多かったのである(たとえば中華民国行政院賠償委員会発表、1947年) 。
一方「内地」にあって「唯一」の地上戦が展開した沖縄では凄惨な戦いとともに、「大和」の自殺(特攻出撃)と似て非なる「集団自決」が叢生した(比嘉富子『白旗の少女』ほか)。
さらに前線ならざる都市爆撃、そして一瞬で夥しい破壊と膨大な数の死者を生じさせ、生き残った者の骨髄をも蝕みゆく原爆は、先の大戦から今日に至る戦争と戦略の著しい特徴である(原民喜『夏の花』ほか)。
そうして都市とインフラ、生産システムの完膚なきまでの破壊は、戦争が終結した後も食糧をめぐる悲惨な状態を現出せしめたのである(野坂昭如『火垂るの墓』ほか)。
「戦争文学の最高峰」などという表現がそもそも「笑止」なのは、たとえば先にあげた二つの「うた」に「戦争」が描かれているわけではないからである。
ここに並べられているのは「戦争」ではなく、「いくさ」に駆り立てられ、赴かんとする者の、出立の心情とそれを鼓舞する言葉であって、それ以外ではない。であるからこそ、逆に「心ゆさぶられる」(高揚させられる)のである。
「『戦友別盃の歌』がはじめて『うなばら』(当時は赤道報といった)に出た時の感激は大きかった。将校も兵士もその感動を隠さなかった。歌のところだけが切り取られ、手帖に秘めて愛誦された。(略)ある若い将校は私に語って言った。『長いこと詩を忘れてゐたのが、大木さんのあの詩で、詩の存在に気づき、詩が如何に大切なものかをはっきり知ることが出来たのを喜んでゐます。戦場と詩といふものほど離れてゐるようで実はしっかり結びついてゐるものは恐らく無い筈ですからね』と。(後略)浅野晃」
「戦争に於て勝敗を決するものは、兵の数でもなければ装備でもなく、人間の、民族の、精神力の凝集したものであると同時に、人間の、民族の、表現力が凝集したものは詩であることを知ったのは、僕にとっては大きな発見であり、啓蒙であった。かつで僕は『詩人認識不足論』を書いて日本の詩壇を騒がせた男であるが、その際何の反駁もしなかった大木君に対して、今の僕はただ黙って頭を下げるほかないはない。/戦争といふものは実に素晴らしい文化的啓蒙者である。大宅壮一」
上掲2文は、宮田毬栄著『忘れられた詩人の伝記 父・大木惇夫の軌跡』に『海原にありて歌へる』の「跋」から引用されているものである。そうして著者すなわち大木惇夫の次女は次のように書くのである。
「父の戦場での詩の働きは、ジャワ方面軍の首脳部が予想していたものを遥かに超えていた。宣伝班員のだれもができうるかぎりの仕事に励んでいたが、父の仕事はひときわ直截的な効果をもたらしたのだった。それは詩というものの力にほかならなかった。「詩人大木惇夫の任務は十二分に果たされた」との判断によって、父に帰国をうながす意向が伝えられたのは、胃痙攣の発作で寝込んでから数日後のことであった。」
巻末の年譜によれば、大木惇夫が「現地除隊の形で極秘の帰国」をしたのは1942年(昭和17)9月下旬という。
この時期、戦争は死の翳の下ではあったが、まだその上半身を白々と露出させていたにすぎなかった。
それが赤く黒く黄色の巨大な姿を誰の目にも明らかにしはじめる(「赤く蒼く黄色く黒く戦死せり」 渡辺白泉)には、大木が「任務を果たして」から半年も要しなかった(吉田嘉七『ガダルカナル戦詩集』)。
言葉は人類の虚構の根源である。民族語は「民族」の虚構であり、うたはその直接力である。戦争の「現実」が、「うた」の虚構と乖離を甚だしくすれば、うたは色あせる。「飢え」はその最たる「現実」である。
二つのうたは、つまるところ「行きはよいよい」うたであって、マルスの凛々しくも蒼白い若者顔とは裏腹の、目鼻のない化物の本質に迫るもの(「戦争が廊下の奥に立つてゐた」白泉)ではなかった。だからこそ、うたは「役目を果たし」えたのである。
戦争は、「いくさ」と言われた古代のそれとはまったくの異次元に移行していた。「銃後」もすでに消えていた。「感状」も「勲章」も無意味であった。その結末は、死と廃墟と飢えであった。「帰り」を生きた「生き残り」たちは、当然ながらこれらのうたとメロディーを記憶に封印し、それを見聴きするのを好まなかった。すくなくとも私の父はそうであった。「アウシュヴィッツ以後、詩を書くことは野蛮である」(T・アドルノ)。東アジアにおいても加害と被害を問わず、同然の「記憶」が刻印されたからである。
「うたびと」は、地獄へつづく「言葉の片道切符」しか手渡さなかった、あるいは手渡し得なかったのである。
これらのうたが今日再び「戦争を知らない世代」の間に浮上し、あるいはわれわれにある種の「感情」をもよおさせるとすれば、さらに切開しなければならない問題が残ると言わなければならないのである。