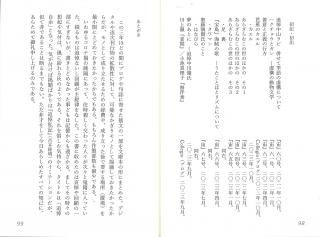上掲は本日刊行、製本150部の文庫本である。
部数としては前世紀の「ガリ版印刷」以下のレベルだろう。
製作費を最小限に収めた結果だが、目いっぱいの価格(本体1000円)を付しても、原価率は50%である。
つまり正味6割、送料版元持ちのAmazonはもちろんのこと、正味7割の一般書店でも販売は不可能であるから、ISBN(978-4-902695-38-0)やCコード(0195)は付したものの、直売しか手段はない。
つまり直売以外は行わない。
150部のの3割は献本に費やさざるを得ず、残り100部が直販完売してようやく原価回収となる。
それが達成できることを祈るほかない。
もちろん献本先からも「投げ銭」はもろ手を挙げて歓迎したいが、さて。
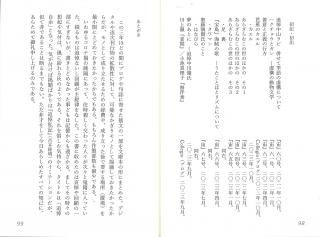
わたしたちはいま、わたしたち自身が現に生き、活動している生活の舞台を、地域や国家などの概念をとびこして、直接にひとつの惑星の部分として具体的にイメージし、たしかめることができるようになっている。これはもちろん人工衛星などの科学技術の発達によるところがおおきいのだが、また、あたらしく普及した地球生態系的世界像の産物ともいえる。
これは、人間が自分の姿を可能なかぎり遠距離から、また可能なかぎり直接にかえりみる手段をもつことができるようになったということである。そして、そこにみとめたのは「自然」としての文明の姿であった。その意味では、地図というものを、現代ではまったくあたらしい視点から見なおさざるをえないようになってきているのではないか。
フィールド・ワークをもとに思考をくみたててきたわたしは、地図を不可欠の道具として利用してきた。それは、単に道案内のためではなく、ひとつの自然像、ひとつの文明像を把握するための材料としてきたのである。地図はわたしにとっては、ひとつの「博物館」であった。
今回、柏書房から発行される『日本近代都市変遷地図集成』は、道具としての役わりを終えたふるい地図を、あらたに編成し直すことによって、わたしたちの生活の舞台である都市を、今日までの約100年の時間距離のなかでとらえなおすこころみといえるだろう。
古地図は資料であると同時に美術品である。個人や機関に分散して秘蔵されているため、博物館や図書館でも一定地域のものを系統的に紹介するのは容易ではない。今回の出版のように、都市の変遷を示す材料として集成された例はすくない。日本の都市文明の足どりを、あらたな視角から見なおす作業をいざなうものとして、このアトラスはひとつの知的生産の出発点となろう。
以上の文章は、『梅棹忠夫著作集 第21巻』(1993年)のpp.304-305に収録されている「『日本近代都市変遷地図集成』―すいせん文」の全文である。
梅棹忠夫氏(1920‐2010)は生態学や人類学で独自の学問を切り開いた著名な学者で、最初期の著作『モゴール族探検記』(1956年)もベストセラーとなって、そのころ小学校高学年か中学生であった私も読んだ記憶がある。
この「すいせん文」は、1987年に柏書房から刊行した『日本近代都市変遷地図集成』の「内容見本」に収載したもので、当時柏書房から刊行されていた大型地図資料は私がほどんど一人で編集し、推薦文も私が電話で直接依頼したのである。
しかし梅棹氏は原因不明の病により1986年3月にはほぼ失明状態となっていて、推薦文は文案を書いて送れとの指示であった。
おそらく秘書役の人がそれを読んで聞かせたのであろう。
文章は加除訂正なしでOKとなり、内容見本は無事刷り上がった。
その3ページに掲げられた梅棹推薦文のタイトルは「系統的に編集された知的生産の出発点」で、これも私が付けたものであった。
その何年か後、これも秘書役の男性だったと思うが、電話で、かの推薦文は著作集に入れたいと言うので、嫌も応もなく了承した。
いずれにしても上掲の文章は、私の筆になるものである。
いま読みかえしてみると梅棹氏の著作よりも、『試行』に連載されていた吉本隆明氏の「ハイイメージ論」(後単行本、文庫本)の影響が大きいようだが、しかしイメージそれ自体は、以前から私が「ヒト群落」について思い描いていたことに端を発している。
文中の「「自然」としての文明の姿」とは、実は1972年頃離陸する飛行機の窓から見た、光るスモッグドームに覆われた大阪圏の姿であって、露骨に言えば微細な虫の巨大コロニーないし地表の腫瘍というイメージにほかならないのである。
ヒトが地上に生きるエリアとその態様は、とりわけこの100年の間に劇的に変化した。
「アントロポセン」が提唱される所以である。

知人の編著で上掲の本が上梓された。
宮田浩介編著、小畑和香子・南村多津恵・早川洋平著。学芸出版社から2023年11月10日刊、2400円。
「車中心の100年で失われた人のための街路」をとりもどす、ために。
スポーツや趣味、スタイルとしてのサイクル文化ではなく、すべての人のための自転車インフラを目指して。
そのような編著者らの主張とその実現への努力に、惜しみない賛意と敬意を呈したい。
そのあとがきの一部を以下に掲げる。
「初めて自転車に乗れた時のこと、左右のペダルの推進力をつなげ、ついに「離陸」した瞬間を覚えているだろうか。自転車は人にささやかな羽を与え、人を世界から切り離すことなく、世界を新たに発見させる。それは子どもでも使える身近な魔法であり、日常の中の祝祭である。/本書で目指したのは、「人」から出発して自転車の街を語ることだ。ただ通り抜けるだけではない。人が世界に触れ社会に関わっていく場としての道を増やそうと考えた時、想像力のキャンパスに描かれる人々のそばには、おのずと自転車の姿が浮かび上がってくるはずだ。(略)私たちの「公共」体験の大部分をなす日々の移動。その形態は、なによりもまちと社会の構造に強く決定づけられ、反復が他の可能性を忘れさせている。(略)なすべきことはあまりにも多いが、漕いでいる限り倒れはしないし、どこかで追い風も吹き、光も射すだろう」
蛇足だが、この本に目を通しながら思い出したのは、バスに乗ると目にする「自転車は乗ったらあなたもドライバー」という575標語。
この本で紹介されているような世界的な環境整備の動きに気付くと、これはその経路をネグレクトして、当面は自転車に乗る側に責任を押し付けて済まそうとする、手抜きのための標語に見えてくるのである。
前回紹介した当該書にかかわる雑誌記事を、以下順番に紹介する。
まずは初刷り刊行ほぼ1月後の『朝日ジャーナル』誌1964年12月13日号の書評である。
「自然をかえてゆく人工」
最近のわが国経済のいわゆる高度成長にともない、国土ははげしく変貌しつつある。その様相は、とくに大都市においてはげしい。土木技術の進歩により、従来は考えられなかった大規模工事が可能となった。それで都市の再開発は、都市の顔を見違えるほど変えてしまうようになった。変わってゆくのは顔のみではない。地盤沈下によく象徴されるように、現代都市の深部では、自然そのものさえ変質しているのである。
「現在ならびに将来の東京は、人工が自然改変の第一の力となり、それによって良くも悪くも改変されると考えられる。そしてどのような改変が良い改変なのかは、東京の自然の深い理解と考慮の上に求めねばならないだろう。また、東京の土地利用は、家屋密集地ほど地盤が悪く、水害や火災の危険にさらされている、といった面が少なくない。このような土地の不合理な利用を改めることも東京の重要課題であろう」と著者は主張する。
東京の地形・地質
東京湾満潮位以下のいわゆる0メートル地帯は、国電環状線内の面積よりも広い。この低地は、過去約千ないし二千年間に、主に自然の運び出す土砂で埋立てられ陸となったのに、それがわずか五〇年間に再び海面以下の土地となってしまった。この一例でも、これからの東京開発には、土地の性質をよく知って、長期の見通しを持つ必要がある。このような立場で、著者は、現在の東京の自然がどのようにしてできたかを、数多くの学術文献、官庁の地盤や地質調査報告などに基づいて、じゅんじゅんと解説する。
全編は、(一)東京の自然、(二)武蔵野台地の土地と水、(三)氷河時代の東京、(四)下町低地の土地と災害、(五)東京湾の生いたち、(六)むすび、より成る。東京都民にとってなじみ深い各地点の地形・地質とその成因が、本書を通読すると、一通りはっきりしてくる。しろうとにはややわかりにくい学術用語も散見されるが、説明はていねいであり、多くのわかりやすい地質断面図などの図形が五三もあり、理解を大いに助けている。とくに武蔵野台地の地形・地質とその発達史的解説、関東ローム層の分布や厚さとその生成発達に関する詳細な解説は、著者ならではの念の入ったものである。
これらの説明が、国電や私鉄の車窓からの視角にも注意を払っているので、一読後、東京の工事現場や車外の景色をながめるのが、だれでも非常に興味深くなるに違いない。山手にはなぜ坂が多いのか。むかしの富士見の名所。隅田川以東にはなぜ高層ビルが少ないのか。地震の被害はどんな地層の場所で多いのか、といったさまざまの疑問は、本書によって地形・地質的にはっきりと知ることができるであろう。
開発計画への忠告
しかし、本書の意図は、そのような地学的興味を満たすためではなく、冒頭の引用にもあるように、これから人為的に激しく変革すると予想される東京の開発計画に、確実な地学知識の裏付けがいかに大事であるかを読者に認識させるにあるようだ。
というのは、現在では実際の工事計画者や施工者と、地学および考古学者らとの連繋ははなはだ不十分であるからだ。たしかに工事に先立ってボーリングなどの調査はかなり行われるようになったし、掘さく中に小判や人骨でも出れば必ず考古学者が出動するであろう。しかし、そのような協力は本質的な協力ではない。宅地造成、地下鉄、地下街、高速道路、マンモス・ビル、などの大工事にともない、最近の東京では、大量の土砂が掘られ、運ばれ、埋められている。しかも、この傾向は今後ますます強くなるであろう。
先進諸国では大きな開発に当っては、計画段階から必ず地学者や考古学者が加わっている。それによって、現在の土地の特性を計画におりこむことができる。のみならず、著者が力説している、地盤沈下などの災害要因を含めて、開発が自然に与える影響も長い目で推測することができるであろう。
著者も指摘しているように、現在の東京では工事などで現れた地学上の重要断面なども、地学者の目にふれず永久に埋めもどされ、学術上貴重な発見があたら失われている例が多い。そのような損失を避けるためにも、これからの開発に当っては、建設技術者と地理学者たちとの密接な協力体制がきわめて望ましい。技術の進歩と経済の発展が、とくに大都市において自然を変えうるようになった現在、それはおそらく都市計画の成否を左右する一要因とさえなるであろう。
その前提として、東京都民なかんずく建設工事などどなんらかの関係のある人びとが、啓蒙書として書かれた本書の内容を常識として体得することが強く望まれる。さらには、将来の東京を築く、高校生や大学生諸君が、この程度を常識として東京の地形を車窓からながめるようになることを希望したい。(東大助教授・高橋 裕)
この時点から59年を経ようとしている。
都市開発と地理・地学との「協力」はどうなったであろうか。
かつての、そしていまの高校生や大学生が、『東京の自然史』の要点を「常識」としているであろうか。