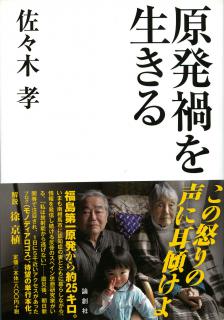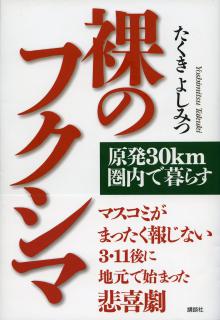1983年に発売されたチェッカーズのデビュー曲は、康珍化作詞、芹澤廣明作曲の「ギザギザハートの子守唄」だった。
筆者は20年ほど前、時々この曲をカラオケで歌って顰蹙を買ったものだ。
近年は歳相応に衰え、酔うために朝方まで酒を呑む、というようなこともなく、加えて昨今は呼吸器系統がダメージを受けて、いまだそれをひきずっているものだから、歌の記憶からは遠ざかる。
しかし、「ギザギザ」には突然遭遇してしまう。
人と話をしていて、お互い急にギザついた感じになってしまうのだ。
「被曝」の影響などという話題に不期して触れてしまうとき。
観点を異にした者どうしがそれぞれマグマをかくしもっているものだから、互いに鎧袖一触。
A)
「被曝の影響などと言うが、煙草の害や排気ガスと比べると、そちらの方が深刻」
「内部被曝の影響を心配して、子供に給食を食べさせず、弁当をもたせるような親は、自分の子供のことだけを考えている(そういう親はデモにも行かないだろう)」
「被曝の影響が実証されないかぎり、言い立てるのはおかしい」
B)
「被曝は空気や水、食物にかかわる万人の問題で、煙草や排気ガスなどの汚染と比較してはいけない」
「被曝を避けたり逃れたりすることのできる者はそうすべき(生物として自然の行為には、卑怯もエゴもない)」
「被曝の影響は事故を概括して考えるべき。チェルノブイリ(1炉事故・短期間)と、フクシマ(3炉+4燃料プール・いまだ未収束)を比較しただけでも、今回の事故の巨大さが判断できる」
以上は、Bの側からのまとめだから、衡平を欠くものだろうが、手掛かりのためにとりあえず掲げてみた。
ニュアンスの違いや漏らした論点も多いかもしれないが、こんなものだろう。
排気ガスや煙草の害といったステージのまったく異なるものを引張り出す手法は3・11当初から存在していたが、それがリアリティあるもののように主張され、受け入れられえるのも、首都圏に住まう人間にとっては、現状肯定、日常化現象が必要だからなのだろう。
しかし、本当に「ギザギザ」なのは、巨大な原発「事故」そして人類史上空前の被曝という「人災」に対して、司法がまったく動かないことだ。
昨今の「オリンパス粉飾事件」ですら、東京地検は「幹部聴取」を開始するという。
強きに弱く、弱きに強い、のが司直の常だとすれば、中国あたりを「法治国家ではなく人治国家」などと言っていられないはずだ。
知人に示唆されて、あらためて幸田露伴の高名な文章にひととおり目を通してみた。
岩波文庫『一国の首都』のタイトルには、「他一篇」と付けたりがあって、その短い一篇は「水の東京」なのだが、そちらは必要があってすでに馴染みの文章であった。
しかし、メインの「一国の首都」を通読するようには、食指が動かなかった。
明治32年11月、一気呵成に書かれたといわれるが、現代人にとっては見慣れぬ漢語をちりばめ、見出しや章区切りもない、11万字余りのその文は、気軽に読み下せるものではない。
そうしてまた、劈頭の一文からして、その後を目で追う気を失わしめるのである。
曰く、「一国の首都は譬(たと)へば一人の頭部のごとし」と。
確かに「首都」というタームからしてみればそうだろう。
しかし、これは明らかにcapital cityの翻訳語であって、その本意は「首都」ではなく、「主都市」なのだ。
ひとつの国家を前提とし、その政治の府たる場を人体の頭部に比喩するのは、きわめて凡庸な「アジア的」スタイルである、としか言いようがない。
岩波文庫の巻末には中野三敏が注し、大岡信が解説を書いているが、それによると、書誌学者にして明治文学研究で知られる柳田泉はその著『幸田露伴』(昭和17年)のなかで、「一国の首都」は「曠世の奇文」であり、「この一文だけでも露伴の名は永久に伝はることが出来たらう」と絶賛している由。
大岡もつづけて、この文に「何らかの意味で匹敵しうるだけの包括的で懇切丁寧な東京論を書き得た人が他にいただろうか」と問い、「一人もいない」と結論づけている。
果してそうか。
3・11以降の事態は、従来の都市論や首都論がまったく説きおよばなかった異貌の東京の姿を露出させた。
そうして、実はその異貌の東京は、明治30年の3月に、足尾銅山鉱毒被害地の住民2000人が徒歩東京を目指し、警察の阻止線を突破した800人が日比谷に集結した時にも、また水俣病患者の代表らが上京した昭和44年4月にも、厳然として存在していたのである。
幸田露伴の「一国の首都」の後半35ページ、つまり全体の30パーセントあまりが、都市における「娼家制度論」となっていて、露伴の「博識」のほとんどはここに表れているのであって、まっとうな都市論としてはすでにバランスを失している。
その情熱、その博識、その文章力において、多分露伴は何人をも寄せ付けない、ぬきんでた才をもった人物であったろう。
しかし、その人物や才能と、そこから生み出された作品とは区別されなければならない。
今日この「都市論」は、及びもつかないと仰ぎ見られるのではなく、その内実に沿って、批判的に読まれるべきである。
そうして、この文章から今日くみ取るべきものがあるとすれば、例えば、駅前に簇生せる簡易賭博場(パチンコ、スロットの類)や簡易買売春店舗(テレクラの類)、そしてサラ金事務所とそれらの看板を一掃できないのは、すでに政治と民心が江戸後半あるいは末期の様相を呈しているからである、という読み換えが可能だという点にあるだろう。
東京は、そして「首都圏」は、ストロンチウムを持ち出すまでもなく、いまたしかに、末期の姿を呈しているのである。
「地方出版の雄」のひとつに数えられた福岡の葦書房から、その本が出たのは1980年の11月だから、30年以上昔のことになる。
上に掲げたタイトルをもった書物のことだ。
気になって、ずいぶん探して書函の底から引張り出し、再読してみた。
著者は、その18年後に同書肆から『逝きし世の面影』を上梓し、和辻哲郎文化賞を受賞することになる渡辺京二氏である。
3・11を契機に赤裸々に露出した、日本における[首都/地方]のグロテスクな図式を、どのようにこの伝説的著者は「解」したのだったか、それを確かめたかったのである。
氏の、「都と田舎の関係」についての予言はこうであった。
「東京対地方という問題の立てかたの根拠は、進展する全国的な都市化の波、劃一的均質化の動向によって、遠からず消滅するだろう」と。
もちろんこれは、都市化の波を危惧し、「地方の復権」を異口同音に求める「地方文化人」のなかにあって、反語的に主張された論であった。
しかし、「突出した首都」という、「古代的」あるいは「アジア的」な構図は、すくなくとも「遠からず消滅する」ことはなく、むしろ「首都の懸絶した大きさ」は、今日の世界的現象として指摘される。
あるいは、1%と99%のうち99%の半数以上が、首都に吸い上げられ、漂わざるを得ないのが現況であると言い換えてもよい。
氏の立論が、「地方文化人」たちの俗論に対する反動の域を出なかったのは明らかである。
「田舎」がいかに「電化」あるいは「情報化」され、コンビニが遍在し、ゴミ回収車がくまなく集落をまわるようになり、風景が均質化されたとしても、それが「都と田舎」の平準化を結果したわけではない。
なぜならば、人間そのものの「能力」序列において、その頂点から首都に回収され、国家に序列化される社会的価値のヒエラルキーはむしろ高次化したからである。
「価値」は、一極から垂れ流される。
それは、現代社会の「グローバル」な結合と、高度複雑化によって、必然的に巨大化する国家官僚システムと世界資本の運動にパラレルな現象である。
かつて「都市論」や「国家論」がジャーナリズムをにぎわせた時代があった。
羽仁五郎の『都市の論理』という書物はそのひとつであったが、今日それを顧みる者は誰もいない。
対して、増田四郎の『都市』は、なお味読に値する名著と思われる。
ただし両著の論旨は、ギリシャ-ヨーロッパ史の一定時期、都市は国家に包摂されず、分立、拮抗しており、制度としての商人・職人のギルドも、社会の分節として実効されていて、その「記憶」こそ「民主主義」の、実際上の淵源であった、という点で一致していた。
しかし、その規範としたヨーロッパ史自体が、歴史的思想的相対化を避けえない領域に、人類は踏みこんでしまったのである。
あるいはこう言い換えてもよい。
生物としての人間存在(人口)と、その空間的結合度の規模が、「民主主義」で解決できるほどのスケールを超えてしまったと。
つまり「現代世界」の、すくなくとも政治経済の一側面は、分節した「地域」と「社会」を備えたヨーロッパ式結合ではなく、国家官僚がすべてを統制する「古代アジア的形式」にかぎりなく近接するのである。
これを、「中国の世界化」あるいは「世界の中国化」と言えば、口が過ぎるだろうか。
「地方」の「都市化」とは、そのような世界的変容の末端現象であった。
渡辺京二氏の、30年前の楽観論の破綻の先に見えてきたのは、今日の「世界」の、すくむような立ち位置そのものである。
都心部の高級賃貸マンション、その多くは「外人」が利用していたのだが、その価格が半値ちかくにまで下がっているという。
六本木ヒルズの「外資系」オフィスも、実質ガラ空きという話もある。
「風評」とは、流言蜚語ではない。
株価同様、市場原理のひとつである。
そのかぎりにおいて、風評はモノの価値あるいはそれがおかれた実態を正しく指し示す。
「岡目八目」ということは常にある。
天津や大同あたりで原発事故が起きたら、北京在留の日本人の多くはさっさと引き上げるか、上海に拠点を移しただろう。
危機は、傍目にこそ明白に、あるいは的確に映るのである。
日本人の多くは、職場や学校の関係上、そう容易くは動けない。
だから、「現状」に合わせるように、希望的に、将来を「観望」するのだ。
そうして、多くの日本人の、とりわけ働き盛りの男性が口にするのは、表題のような「そのときは そのとき」という科白である。
しかし、「そのとき」どうするというのだろう。
多分何も出来ない。
自分の頭で考えることを放棄した人間に、自分の次なる行為を選択する余地はないからだ。
政府や行政、消防や警察の勧告や指示に従って、黙々と行動するしかないのだ。
それすら機能しなくなったときは、パニックに陥って、やみくもに遠くに移動しようとするだろうか。
ここに2冊の本がある。
佐々木孝著『原発禍を生きる』(論創社、2011年8月20日刊)。
鐸木能光(たくきよしみつ)著『裸のフクシマ』(講談社、2011年10月15日刊)。
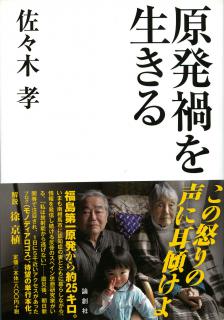
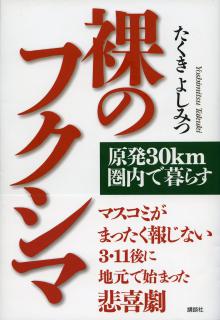
世代は異なるものの(前者は1939年生まれのスペイン思想史家。一方は1955年生まれの作家)、著者はともに上智大学出身。
そうして、ともに「東京」のために引き起こされた、史上最悪の人災下に今なお住み続けている人々のひとりである。
その「地域」からの言葉は鮮やかであり、重く、飄逸ですらある。
とりわけ佐々木氏の著書の65ページに記載された、以下のような「実話」は、人間の究極の「尊厳」というものを示しているように思う。
珠玉の一節である。
「時おりあのおばあさんの姿が目の前にちらつく。双葉町だったか、10キロ圏内ながら迎えに行った役場の人に向かって避難することを丁重に断って家の中に消えたあのおばあさんである。その後あのおばあさんはどうなったかは知らない。しかし毅然とした彼女の態度が、胸に深く刻まれたままである。
確かにあのとき、家の中には病人のおじいちゃんがいたのではなかったか。「私は自分の意思でここに留まります」といった意味の老婆の言葉に、困惑した迎え人がつぶやく、「そういう問題じゃないんだけどな!」
いやいや、そういう問題なんですよ。君の受けた教育、君のこれまでの経験からは、おばあちゃんの言葉は理解できるはずもない。ここには、個人と国家の究極の、ぎりぎりの関係、換言すれば個人の自由に国家はどこまで干渉できるか、という究極の問題が露出している。」
そうしてこの場合、「国家」とは「地域」に、「迷惑施設」を強制した挙句、文字通り未曾有の災害を引き起こし、人を「根こぎ」に追い立ててなお平然を装う下手人本人にほかならないのだ。
われわれ一人ひとりが、圧倒的な物理力と強制力をもつ「国家」を相手に、なお尊厳を失わないとすれば、それはどのようなことなのか、われわれがどのような時代に生きているのか、この文章は指し示しているように思われる。
数年以上前から、9月も半ばを過ぎるときまって体調がくずれ、咽喉の痛みと微熱に悩まされてきた。
けれども今年は少し様相が異なる。
3月半ばから鼻の奥に異物感があって、オカしいと思っていたら咽喉に来て、9月には咳となった。
今、朝夕がつらい。
喘息とはこういうことを言うのか、と思わされる。
ちょっとの寒さがひびくので、外出には毛糸のキャップとマスク、マフラーが必需品となった。
いろいろ探して、ネットで肩蒲団なるものを見つけた。
不格好だが、家では昼間も着けている。
手首、足首も何か巻くものが欲しい。
医者に行ったらレントゲンを撮られて、専門医に紹介されたが、専門医もとくに異常は見出せないという。
アレルギーの薬を処方された。
しかし、薬は一向に効かず、現実に、とりわけ朝夕は苦しい。
あきらかに体の免疫力が低下している。
内外の被曝の影響は、個人によって千差万別である。
東電原発立地エリアでなくとも、東日本に住まいしている以上、何人もその発症の可能性について、一笑に付すことはできない。
還暦も過ぎたほどの人間は、多少の被曝は仕様がない、問題は子どもたちだ、というのは「正論」である。
しかし、「被曝する」ということは、身体的にも精神的にも「苦しむ」ことにほかならない、というのは、この喘息でよくわかった。
だから、むしろ「正論」は、何人といえども、できるだけ被曝を避けるに越したことはない、ということになる。
災厄咽喉元を過ぎ、「冷温停止」などという言葉になんとなく日常に返ってしまった「東京」だが、「最悪の事態」の可能性はまったくそのままである。
「保安院」も、最近こっそりシミュレート発表した「4号機の倒壊」の可能性である。
使用済核燃料1535本が、原子炉建屋の5階にプールの水に浸けられて、四六時中熱交換器で「冷却」されているけれど、この建屋自体が傾いている。
いま、世界中の「専門家」がもっとも注視しているのはこの4号機で、なんらかの「事象」が発生すれば、首都圏などひとたまりもない。
日本の大本営は「勝利」や「神風」、「転進」などという幻影をふりまいた挙句、都市部の徹底空爆・原爆攻撃をゆるし、最後には降伏するほかなかった。
今回もまた同じく、危機がまったく過ぎ去ってはいないのに、「復興」幻想をふりまきつつある。
現実に存在する危機の可能性を「杞憂」とは言わない。
それを無視したり、軽視したりするのでなく、正面から受けとめ、説明し、対処するのが「おとな」だろう。
聞きたくない、見たくない「現実」に耳目を逸らさないのも「おとな」だろう。
「日本人」は、子どもばかりか?
東京の東北端、埼玉県三郷市と千葉県松戸市に境を接する水元公園は、江戸時代の小合溜井(こあいだめ)という灌漑用の遊水池をひきついだもの。
けれどもそもそもは、古利根川の旧流路の蛇行跡。
だから、雨量次第では昔の河川が復活する。
64年前のカスリーン台風時における、桜堤決壊はその一例。
この一帯には明治以降も、アシやガマ、マコモが繁茂し、季節がくればアサザの黄色い小さな花が咲いた。
ヨシキリも行々子(ギョギョシ)と鳴き、澪筋(みおすじ)を和船が通る、水郷風景がつづいていた。
行々子どこが葛西の行留り(一茶)。
戦前の水元緑地は170ヘクタールはあったのだが、昭和40年に開園したこの公園の面積はその半分ほどになっていた。
それでも23区中最大の面積をほこる。
そこに行くには、金町駅北口から京成バスを利用する。

水元公園の西の一画。対岸は三郷市
しかし、この満々と湛えられた水も、現在は電気仕掛けである。
西につながっていた大場川から、ポンプアップした水を循環させて、水質を維持しているという。
電気が来なくなれば、ヘドロの水溜りと化す。
広尾の有栖川記念公園の池も、吉祥寺の井の頭公園の池も、都内ほとんどの公園の池は同然である。
自然の湧水池といえるようなものは、明治神宮の清正井くらいだろう。
なんといっても、あの周域は人工のサンクチュアリ森林に涵養されているから。
水のある風景まで、電気仕掛けにしてしまった「近代」は、いま末期(まつご)の姿をあらわしつつある。
以下は公園内の数値だが、実はそこに向かう途中、水元公園入口バス停付近側溝口では0.52μSV、水元中学校正門前の植込み表土は0.55μSv。
5ヶ月ほど過ぎてなお、きわめて高い数値が計測された(いずれも2011年8月4日午後)。

2011年8月4日午後、水元公園の刈草の上の数値

空中線量はそれほど高くない。やはり3月時点での降下放射性物質の遺留が影響している
「近代」は、都市域を肥大化させ、「卑湿の地」を剥奪し、あらゆるものを電気仕掛にして止まない。
その挙句が、かくなる結果をもたらした。
「除染」の究極は、都市そのものを地下化したり宇宙船化することになるが、それは結局不可能である。
「地域」にとっては、「近代」そのものが、巨大な災害の時代にほかならないのである。
脱原発ではない。
脱(巨大)電力、脱(巨大)流通・移動こそが、今世紀の人類の着地点である。
国際放送Russia today映像報道。
福島で放射性物質計測中のグリーンピース。
「チェルノブイリの3-4倍のとんでもない量の汚染だが日本政府は市民を避難させない。ソ連でさえした。まるで別の惑星に来たようだ。」
http://t.co/PfFB8Eh
惑星といえば、ピエール・ブール原作の『猿の惑星』はハリウッド映画化されて、それも次々に続編がつくられた。
アタッタのだ。
いまハヤカワ・ノヴェルズで読める翻訳のあとがきによると、原著はPierre Boulle:La planete des singes,Ed. Julliard,1963.となっている。
ブールは1912年アヴィニョン生まれのフランス人。
理学博士であり電気技師でもあって、マレーシアでゴムのプランテーションにかかわり、第二次大戦中は自由フランス軍に加わりインドシナや中国各地を転戦したが、日本軍の捕虜となった。
イギリス軍の援助で脱走、抗戦をつづけ、戦後はパリに戻り文筆を主とした。
1994年死去。
代表作は『猿の惑星』と『戦場にかける橋』である。
その履歴に照らしてみれば、「猿の惑星」という発想のヒントは日本軍の捕囚となった経験であることが了解できる。
猿が馬に乗って、三八式鉄砲をもってやってくる、というわけだ。
チンパンジーも、オランウータンも、ゴリラもいる。
もちろん、会話が成立する理性的なチンパンジーで、最後は脱走を助ける者もいる。

「猿の惑星」の一場面
今回の「事象」に照らして世界的な視座からみれば、原発を多少いじることはできても制御できず、事故に対する認識も欠落し、その対処もできない、猿たちが列島惑星にひしめいている、ということになろう。
ことはそれだけに終らずに、その列島から膨大な量の放射性物質を、空中に、海水に拡散させて、なおつづけているわけだから、現行犯猿なのだ。
よく野放しされているものだ。
この猿の頭目は、通常は官僚と言い慣わされている高級国家公務員ゴリラたちだ。
彼らはほとんど終身ゴリラである。
つまり失職しない。
選挙でまがりなりにも民意を体して浮沈のある政治家たちとは決定的に異なる。
その政治家たちが、専門知と情報、実質権力をもったゴリラを統御することはまず不可能だ。
ゴリラたちは、自分の都合のよいように情報を操作し、隠蔽する術に長(た)けている。
ここにおいて、日本の民主主義とは、変わりばえのしない政治家を低い投票率で選ぶ名目上の民主主義にすぎず、実際は中国などとかわらない、マンダリン(高級国家官僚)統治であることが判明する。
マンダリンが責任を問われることはめったにない。
原発事故の最終的な責任は、実は彼らにあるのに、である。
何度も言うが、カンリョー・ゴリラやトーデン・オランウータンたちは、江戸時代なら即縛に就き、獄門、さらし首である。
責任不在の、この一点において、現代日本の政治システムは決定的に誤っている。
責を問われるべきだ。
ただちに裁判にかけられるべきだ。
7万人が家や農地、仕事を奪われてさまよい、自殺者がつづき、何十万人が命と遺伝子を傷つけられ、次世代以降まで影響をおよぼしつつあるのに、彼らが老後をまっとうすることなど、あってはならないのだ。
不正義どころか、犯罪である。
犯罪が放置されるとすれば、放置した者の責も免れない。
そうして、政治システムにおいて、この列島に「民主主義」が存在するとすれば、結局はすべてを握る高級国家公務員が、選挙の洗礼をうけ、失職させられるシステムが確立し、ゴリラやオランウータンを一掃してからの話なのである。
日本列島の放射性物質汚染に乗じて、悪質な「除染企画」が蠢動している。
たとえば線量の高い、葛飾区の「都立水元公園」。
広大な水と緑にめぐまれたこの場所から、除染名目で草木を一掃し、コンクリートとアスファルト、人工芝の「運動公園」化してしまうとしたら、屋上屋を重ねる愚行というものだろう。
まずは局地的気候変動がおこる。
熱帯夜と集中豪雨が倍加する。
そうして、クーラーの稼働時間が延長され、その排熱もますます耐えられないものになる。

23区中最大規模の面積をほこる「水元公園」の入口付近
7月23日放映「NHKスペシャル 飯舘村 田中俊一の発言」。
浜岡原発は安全と発言した田中某(元原子力学会会長、元原子力安全委員会会長代行)が飯舘村の区長宅を訪れて、「除染のために木を伐って、谷ひとつくらい潰して汚染廃棄物処理場にしないと、村人は家に帰れませんよ、ヘッヘッヘ」というわけだから、醜怪(グロ)極まる。
ジャン・ジオノの「木を植えた男」という話は映画にもなったが、この男はその真逆で、放射能で汚染した挙句、村を丸裸にし、汚物を押しつけるわけだ。
そもそもどうして土下座謝罪し、汚染物はすべて自分のところで引受けますと言えないのだ。
村人も、どうして「下手人が何しに来た、とっとと帰らないとぶち殺すぞ」と言わないのだ。
現代日本は「倫理」も「正義」もなく、「居直り説教強盗」が横行する無法列島にすぎないことを、まざまざと示した場面だった。
江戸時代であれば、この男、ナントカ学会の一族郎党含めて、とうの昔に獄門さらし首になっていた。
すくなくとも、きょう日娑婆でちょろちょろできる分際ではない。
基本的な環境が「森林」である日本列島が、もっとも美しくまた緑豊かな土地から、その保水力を奪い、土壌を流出、壊死させ、溢水を誘発する禿げ山と汚染谷の出現に与(くみ)するとすれば、その中心に原発の推進者とその金にぶら下がる愚者たちの行いがあるだろう。
村が村であるためには、すなわち土壌流出と砂漠化を防ぐ手段は、可能なかぎり詳細な「汚染マップ」にもとづいた、村人自身の計画と実行による、きめ細かな除染と立入制限区域設定以外に方法はない。
「外部」の厖大な金(カネ)をアテにすることは、結局新たな「原発依存」にすぎないのだ。
地つづきなんだし、風つづきなんだし、不安ながらも基本的には遠い僻地のことのように思っているけれど、実は東京もしっかり放射性物質に汚染されている。
昨日、葛飾区東金町(ひがしかなまち)七丁目の、カスリーン台風による「桜堤」の決壊場所を見に行ったのだけれど、ひょいと線量計のスイッチをオンにしたら、すぐに警告音(アラーム)が鳴りだした。
30μSv/h以上で、自動的に鳴るように設定されている。ご覧のように地表はかなり高い。

昭和22年、カスリーン台風時の決壊場所に立つ説明板。向こう側は江戸川の土手。説明板の下に縁量計

スイッチをオンすると、アラームが鳴りだすこの線量。1.5mの空中線量は0.28μSV
たしかにここは都内でも汚染濃度の高いことで知られる「水元公園」のすぐそば。
けれども、問題は水元公園とその周辺だけではない。
金町まで帰る途中にあった小さな児童公園(東金町五丁目児童遊園)の、すべり台の着地点。



行政はなんの手もほどこさずに、そのままにしていて、利用者もいつもと変らず、子どもを遊ばせているようだ。
とりあえず、ここにその記録を残しておく(いずれも2011年7月28日午後計測)。
ついでに言えば、文京区の根津二丁目児童遊園内でも、地点によってはもっと高い線量値を検出(2011年6月28日午後、地表で0.57μSv)しましたから、東京の端っこの話だろうと安心しているわけにはいかないのです。
都は新宿の計測値だけ発表して、低いの、基準値以下だのと済ましているようだが、ご覧のように、フクシマなみの高濃度汚染地域(ホットスポット)が実在する。
金町浄水場の水道水の放射性物質検出値も、6月一杯「不検出」と発表しているけれど、国や都道府県の「大本営主義」(嘘と隠蔽)がはっきりしている以上、どこをどう計測して「不検出」なのか、疑ってかかるのは「庶民の知恵」というもの。
これを別の言葉で言えば、「風評」という名の「市場原理」なのだ。
最近、東京税関が、飲料水の輸入量が「過去最大」となったと発表したのは当然のこと。
東京が「中央」の顔をしていつまでも平然としていたら、結果は惨いものになるだろう。
東京も、ひとつの地域、地方にすぎないのだ。
天災だろうと人災だろうと、現場を歩き、しらべつくして発表し、必要な措置をとることは、税を徴収し、それで成立している行政体(国、都道府県、市区町村)の義務だろう。
それをやらないのは、顔も心も、住民の側ではなく、「上司」を向いているからだとしたら、一党独裁のどこかの国と変らない。
それでもやらないなら、誰かが記録し、それを遺していくしかない。
遺すといえば、一人ひとりが髪の毛を数センチ、20本ほど切って、とっておくべきという提言がある。
自分がどれだけ汚染されたか、重要な証拠になるはずと。
いま、ネットで大変話題になっている、2011年7月27日 (水) 衆議院厚生労働委員会における「放射線の健康への影響」参考人説明(児玉龍彦 東京大学先端科学技術研究センター教授,東京大学アイソトープ総合センター長。この参考人説明を、NHKは放映しなかった)のサイトを、私も念のため下に掲げる。http://www.youtube.com/watch?v=O9sTLQSZfwo
東大には、アイソトープは飲んでも大丈夫と言ったデタラメきわまりない「教授」もいれば、このようなまっとうな教授もいたのだ。
児玉教授が怒りをもってまず明らかにした、「チェルノブイリ事故と同様、原爆数十個分に相当する量と、原爆汚染よりもずっと大量の残存物を放出した」は、「産経ニュース」の悪質な風評拡散である、「1960年代と同水準、米ソ中が核実験「健康被害なし 東京の放射性物質降下量」(2011.4.28)を完全に吹き飛ばした。
1月以上の御無沙汰。
この間、腰の痛みが左から右へ転移。
これもradiationの影響か?
村では、復興と絆を祈念して、例年この時期に行われる、草野心平をしのぶ「天山まつり」を、特例のようなかたちでやるという。
23日の土曜日。
モリアオガエルの縁、蛙の詩人草野心平以来東京者が接待を受ける「祭り」のようで、いつもはあまり気のりしないのだけれど、今回は特別だから押して1泊で出掛けた。

2011年5月12日の東京新聞から。「緊急避難準備区域」内であっても、川内村の過半は「クールスポット」であることがわかる
川内村は、フクシマ第一原発から30キロ圏内(一部20キロ圏内)にあって、自主的に「全村避難」した。
避難者の「一時帰宅」第一陣報道で知られることになった村だが、実は放射性物質汚染は周辺の市町村に較べてエアーポケットのように低い。

蝉時雨につつまれるから蝉鳴寮(セミナリオ)

キキョウの花は毎年咲く。花の中に、時々クサグモが陣取っている。時に0.36まで上がる。
もちろん場所によってかなりの程度差があるが、村の旧はやま保育所を改装したウチ(別荘兼倉庫。蝉鳴寮:セミナリオと命名)は、写真にもあるように、概ね0.31マイクロシーベルト/時。
2011年7月24日午後2時前後、福島県双葉郡川内村上川内の、地上約1.5mの数値である。
この程度なら都内のホットスポットと大差ない。
とはいっても、一般人の年間許容量1ミリシーベルトとすると、内部被曝を考慮しないでもその2倍半はカブることになる。
0.30を超えると警告音(アラーム)が鳴るので、やたらうるさい。
しかし、村の他の地域、西側の山腹などでは、その倍以上の数値となっているようだ。
全体としては奇跡的な低汚染地域であるからこそ、可能な限り詳細な汚染マップが切実に待たれるのだ。
下の写真のように、同一敷地でも、微細な条件によって汚染度に濃淡がでる。

南に面した軒下の、雨落ち部分はとくに線量が高い

放射性物質は、苔が吸収する、というか苔によく溜る。写真はいずれも、2011年7月24日午後2時頃。