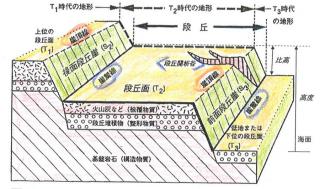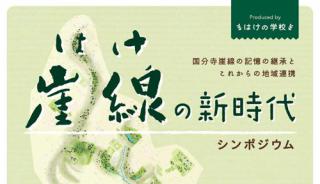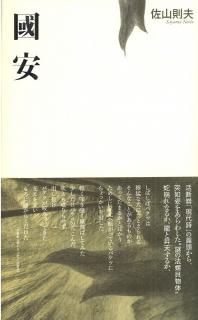東京経済大学国分寺キャンパスに存在する湧き水といえば、新次郎池。
「東京の名湧水57選」のひとつに数えられ、北澤新次郎元学長の名を冠したこの国分寺崖線下の湧水池には、かつては常に清冽な地下水が注ぎ込み、ワサビ田でもあったといいますが、今日では湧き水を目にできるのは1年のうちでも限られた時期だけとなってしまいました。
桜の時期から夏の盛りにかけては、大きな水溜り状態となる新次郎池ですが、8月もはじめ頃には、池の周囲に野生絶滅種とされるキツネノカミソリの橙色の六弁花をいくつか見かけることができました。

8月、夏休みでひっそりとしたキャンパスの、さらにひっそりとした池の森には、今を盛りと咲いているクサギの甘い香りが漂い、クロアゲハが一羽、池の干上がり際にとまっていました。
限られた期間しか湧水を見ないといえども、ここにはまだ野生がいくらか残されている。その証拠に「まむしに注意」の表示板が、池に下りる径の傍らに設えられています。

都会の片隅に野生が辛うじて生きながらえているとすれば、人間やカラス、ネコなどの天敵の襲撃を免れ、採餌を維持し、番う相手もいて、めでたくここまで代をつないできたわけです。注連縄は蛇の交接を形象化したもので、実際のそれは27時間もほどけない情熱的なものといいます(吉野裕子『蛇』、講談社学術文庫、1999)。蝉しぐれのなかで、「ここ」におよぶ何億年かの生命のシークエンス・ドラマを想像するとまことに不思議な気持ちにさせられます。
ところで、都内の著名な湧水池としては、東大本郷キャンパスの三四郎池、明治神宮の清正井(きよまさのいど)、井の頭公園の井の頭池などが挙げられるでしょう。
このうち、自然の水で涵養されているのはたったひとつ、清正井だけ。神宮の森は明治の終わりにつくられた人工の森ですが、その面積と独立した地形が雨水を集め、都心にあっても辛うじて地下水層を維持できているからなのですね。
そのほかの池は、善福寺池や石神井公園の三宝寺池も、そうして葛飾区にある23区最大規模の水郷公園である水元公園の水ですら水源涸渇の結果、電動ポンプで地下水を汲み上げ、それを循環させて水景観を維持しています。都立中央図書館のある有栖川公園の池水も、国分寺駅前殿ヶ谷戸庭園の水も例に漏れない。寅さんの産湯となった帝釈天の水も、お参りすれば手水鉢から常に溢れているものの、それはポンプアップ水。東京の池水公園のほとんどは「電動景観」と言って間違いではないのです。
清正井のほかに、私たちに身近なところで今なお常時豊富な水量を確認できる自然の湧水には、国分寺の真姿の池の湧水群や、国立市のママ下湧水群などが挙げられるでしょう。新次郎池は、限られた時期とはいえ池に注ぐ地下水が見られ、それ以外の時期でも池の水がすっかり涸れあがってしまうということはありません。じわじわとでも、崖(国分寺崖線)からの水は供給されています。新次郎池の湧水は、すくなくともポンプアップされた「偽物景観」ではない。けなげにも、いまだ生命を維持している湧水池というべきでしょう。
水問題を専門とする守田優氏は、井の頭池の湧水が涸渇したのは「一九五〇年代から始まる武蔵野台地の急激な被圧地下水開発が原因である」と断言しています。つまり一般に都市化が雨水浸透域を減殺すると考えられているけれども、すくなくとも井の頭池の場合はそうではないと。深井戸を水源とする武蔵野地区の水道開発がすすみ、「水循環不全」をひきおこされた。深層の被圧地下水を汲み上げると、浅層の自由地下水にまで影響して、湧水は涸渇するというのです(『地下水は語る』、岩波新書、2012)。
翻ってわが東京経済大学の水環境を見てみれば、現在なおキャンパス内で供給される水のすべては250メートルもの地下から汲み上げる深層地下水であって、この地下水利用は赤坂葵町から国分寺町(当時)に移転してきた1946年以来70年に及ばんとしています。現在キャンパス内ところどころにおかれている「ピュア・ウォーター」機はその賜物にほかなりません。
国分寺町にはじめて上水道システムが完成し、送水が開始されるのは1960年。町に市制が施行されるのは1964年で、1975年に水道事業をすべて都に依存するようになったとはいえ、国分寺市の供給上水量の約半分以上は今なお国分寺町が開発した水源(東恋ヶ窪と北町の2ヶ所)から汲み上げている地下水です(『国分寺水道50年』国分寺市環境部水道課、1975)。
国分寺市域に水道が普及する以前、浅い深いの差はあっても人々は基本的に井戸水ないし湧水(いずれも地下水)に全面的に依存していたわけです。
そうして、例えば日立中央研究所(1942年創立。国分寺市東恋ヶ窪)や、リオン(旧小林理研製作所。44年創立。同東元町)など、水道普及以前に国分寺市域に創設された企業は東京経済大学と同様、いまだ独自の水源を生かしているところは少なくないと考えられるのです。
国分寺市域、そして東京経済大学の地下水揚水量などの数字を挙げるのはまたの機会として、ここでは新次郎池の「半死半生」の現状が、このような「地下水利用」と関係があるかもしれないということ、私たちがキャンパス内で使うトイレの水にも、それは関係しているかもしれないという可能性を指摘しておくにとどめましょう。
往古「水の神」に擬され、そして今日でも私たちがその擬制から恩恵を受けている(「蛇口」)ヘビたちが、すくなくとも今世紀にわたってその生を紡いでいくことができるよう、私たちは「水の場所」を大切にしていきたいものです。
【東京経済大学コミュニケーション学部ブログ「きょうもトケコミ」2016年9月5日掲載】