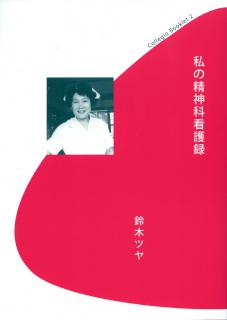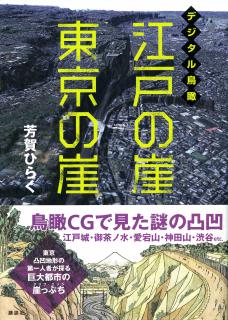というと、松竹梅か鶴亀にまつわるお目出度話のように思われるかも知れないが、
実は思考のパースペクティヴの話。
最近、また書評をたのまれて書いたのだが(掲載紙発行後当ブログでも発表予定)、
レトロや懐かしのイメージのある「昭和」は、
実は、「明治維新」以来進行した「破壊」が、頂点をきわめた時代だった。
何の破壊かというと、「地方」ないし「地域」の、自立と自尊の破壊。
「3・11」はその破壊の舞台裏が、あからさまに露出した事態にほかならなかった。
百年単位、でみるとそういう「透し図柄」が浮上してくる。
これを、千年の視点に転換してみると、現在はその最大破壊を経て、中央集権の「解体過程」に入りつつあることがわかる。
つまり、沖縄は離反し、東北そのほかの地方は、それぞれ「中央」に懐疑と不信をつのらせ、自立に向わざるをえない。
それゆえに、「中央政府官僚」とその提灯持ちは、ナショナリズムに訴えて、中国や韓国と反目の演出をすることに躍起となる。
これを「万年」単位でみれば、結局人間というのはかくも愚かである、という話になる。
あと1万年後に、そもそも「日本」や「日本語」、「中国」や「中国語」、「英語」自体も存在しているとも思えないのだが。
天皇皇后は、本日2012年10月13日、東京電力福島第一原子力発電所から30キロ圏内にある、福島県双葉郡川内村を訪れるという。
総理大臣野田佳彦が10月7日におこなった同発電所の不自然にして唐突な「視察」は、まったくの「露払い」だったわけだ。
事故収束、安全宣言の最大の「カード」として、天皇皇后の現地訪問は、原子力ムラ中枢によって、大分以前から企まれていた。
その候補地が、「奇跡的に汚染線量の低かった」川内村であって、帰村宣言や小学校入学式、運動会の折ごとに、パスチャーターによる巨大な報道イベントが組まれ、大々的に全国報道されたことは、記憶に新しい。その最後最大の山場が、この日なわけだ。
大山鳴動ネズミ一匹、結局のところ原発体制を維持することだけに腐心する、官僚と政府そして産業界の一部等等が存在する以上、
天皇皇后は川内村に慰問に行くべきではない。
川内村は30キロ圏内であるのに福島市よりも郡山市よりも汚染度の低い、いわば「例外中の例外」であって、そこは原子力ムラにとっては
してもいない「収束」の格好の宣伝場である。
天皇皇后が、「除染視察」という「安全ショー」に駆り出される。
天皇皇后も不幸だし、それ以上に日本列島に住む人々、まして汚染された土地から追い立てられた、何万人という人々はもっと不幸である。
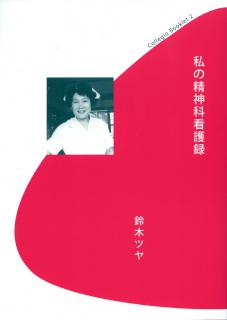
鈴木ツヤ著
『私の精神科看護録』
●精神科看護の原点を求めて―元松沢病院看護婦長の記録
Collegio Booklet 2
A5判262ページ+カラー口絵2ページ
本体1000円
ISBN978-4-902695-16-8 C0347
ご注文

タフィ・トーマス著 三田村慶春・光藤由美子訳
『タフィおじさんのおはなしコート』
●ストーリーテリングの至宝―イギリスの桂冠語り人の再話集
Collegio Booklet 3
A5判106ページ+カラー口絵4ページ
本体1000円
ISBN978-4-902695-17-5 C0073
ご注文
A
私もFacebookの「口座を開」いてはいるのですが、それを開けるとほとんどフリーズ状態に陥ります。
そのため、各方面には失礼の極み、まことに恐れ入ります。
また、メールは発信、着信ともに着いたり着かなかったり。
勝手にロボットがはじいているらしい。
このインターネット半死半生状態は、もちろん一度診てもらおうとは思っていますが、半生のために日々追われて当面はどうにもなりません。
なにかによく似ているようですが、とりあえず弁明とお詫びをしておきます。
B
ところで、
今朝の東京新聞書評欄の「書く人」に拙著の記事が出て、私の写真も掲載されました。
位置としてはページトップで、「寺島しのぶ」の右側、「小熊英二」の上だから、マアマアか。

掲載写真は、東京新聞の女性カメラマンが駿河台の「男坂」の途中で撮ってくれたもの。
季節外れの夏帽子(「夏帽子頭の中に崖ありて」。この車谷長吉の俳句は、石川啄木の短歌のパクリ。『地図中心』2011年2月号拙文参照)をかぶった私が手にしているのは、写真ではよくわからないけれど、福島県双葉郡川内村の燃料店「綿屋」(実際はなんでも置いてある。村長の遠藤雄幸さん宅でもある)で買った「折尺」。
クリノメーター(さすがに綿屋にはなかった)も持っていたけれど、それはカバンの中。
撮影場所は、崖中建築として知られる吉阪隆正設計の「アテネフランセ」を指定したのでしたが、その日はちょうど工事中で入れず、残念ながら近くの階段になってしまった。
その階段も、もちろん「駿河台の大崖」の一部ではあるのです。
C
昨日は京浜急行追浜駅と京急田浦駅の間を歩いて、土砂崩れ、脱線、負傷者の出た現場を撮影。
下はその1枚ですが、崩壊場所は垂直にちかい崖壁面ではなくて、実は崖頂部に近いところで、ロームがえぐれていた。
土砂というけれど、土が崩落していたのですね。

今日は港区三田4-19(旧伊皿子55番地)の崖崩れ跡を探索。
幸田文の『崩れ』に出て来るエピソードの場所で、80年ほど前の崩落。
裏手の三井家の敷地の一部が崩落し、文の家のお手伝いの下半身が泥に埋まった。
高輪大木戸跡交差点から西に上るゆるい坂を右に折れて、少し急坂をつきあたった先は「NTTデータ」のご立派な建物。
旧三井家の門と思われる「遺構」がまだ現役でした。

そこから川崎の生田緑地に転じ、41年前の川崎ローム斜面崩壊実験事故跡地に向いました。
ここは国家機関4つが連合して行った「大実験」だったけれど、予想外の崩壊がおき、31人が生き埋めとなり、15人が即死して大事故となったところ。
慰霊碑とモニュメントが建てられている。

いずれも、9月30日締切の『地図中心』11月号の連載稿用に、超大型台風直撃の前に撮影しておく必要があったためです。
だから、詳細は『地図中心』11月号(10月末発売)をご覧ください。
ところで、事故現場は岡本太郎美術館のすぐ手前で、小さな谷戸の北向き斜面。
美術館自体はその谷戸のどんづまり、谷頭の崖上につくられていたのです。
ゲイジュツはバクハツだ!(岡本太郎)、そしてガケップチだ!!(村野四郎)。
今朝の日経新聞1面右下の「春秋」欄(朝日の天声人語に相当)が、拙著に言及していました。
発売10日目で重版決定ですから、売れているのはわかっていましたが、思わぬところから反響があるもので、吃驚しました。

日経の「春秋」は、この24日の集中豪雨で起きた、横須賀の土砂崩れと電車の脱線事故にからんだ記述ですが、
ちょうど私も、毎月末締切連載原稿(日本地図センター発行『地図中心』の「江戸東京水際遡行」)でこの事故から書き起こし、
40年前の川崎の「ローム層斜面崩壊実験事故」の大惨事(生田緑地の岡本太郎美術館そばに慰霊碑あり)に触れ、
さらに幸田文の短編『崩れ』にまつわる論考(「崩れる」その1)を認めている最中。
川崎の実験事故の「失敗」というか「想定外」のキーワードは、単なる「崩壊」ではなく、ロームの泥流化=「流動化」でした。
民主党や自民党の総裁選の結果、新聞などに登場した、泥鰌や、投げ出し坊ちゃん、の顔写真は、世の中いよいよ「泥流」化してきたことの証のようです。
「美しい日本」を標榜する政治家が、総理大臣になって何ヶ月もしないうちにポイと重責を放り出したと思ったら、またぞろ復活の様相だけれど、
現代日本の、とりわけ都市景観は美しいどころではなく、醜い。
これは、おおっぴらには言われないことだけれど、あきらかな事実である。
その醜さに、さして関心をはらわず、こんなものだと思っているのが一般の日本人らしい。
そうして、京都の一角や盆栽、折紙の「幻想」(イメージ)が、井の中の蛙の脳ミソを占領しているらしい。
街並みだけでなく一般家屋も、たいがい安っぽく、みみっちいのに、モノだけは詰め込んでいる。
寺院や城を除いては、安っぽい家屋が建ち並んでいた江戸時代は、しかし街並み自体は醜くはなかった。
江戸の街自体は、むしろ美しい部類に属していた。
渡辺京二ではないけれど、「美しい日本」は、せいぜい江戸時代までの話。
まあ、現代日本の都市も、歩道をふさぐ電柱と垂れさがる電線、パチンコ屋とサラ金、テレクラの看板とネオン、ビルの屋上の設置物を一掃すれば、それだけで
だいぶマシにはなるけれど、道路にせり出すばらばらの建物とひとりよがりデザインはどうにもならない。
建築家は、個々のデザインや機能を競い、自慢することを止めて、この「醜い」事実を直視するところからはじめるべきだろう。
「地形」に目が向くのは、建築の個別性の袋小路から出たいという衝動だろうが、地形自体を「集め」「分類し」「カタログ」化して
面白がっているだけではどうにもならない。
否定性を媒介としないかぎり、行為は腐臭を放つだけなのだ。
拙著がグラフィックな本となっているため、書店店頭での「類書」との関係で、誤解を生じている面があるようなので、「お断り」のコメントしておきます。
私がこの本で「言外」に主張しているのは、
①「東京の地形」に関して、「景観論」を基本とする言説は概ねダメだ、ということです。
かつて日本建築学会の『建築雑誌』が「新東京地形論」なる特集を組んで、タレントがらみのマチガイ素人談義を得々と展開しているのをみて吃驚したことがあったけれど、
その「風潮」はいまだつづいていて、他人の著作をつまみ食いした「地形カタログ」本が「売れている」らしい。
3・11を経てなお、空虚な論議が人気を得ていて、それが「除染」特需業界の一角から流出している様相には暗澹とするほかない。
拙著の冒頭にも強調したように、見えないところ、見えないものこそ重要なのです。
② ①に関連するけれども、地形は空間論ではなく、時間論のなかで「形成史」として捕えられるべきであり、その場合「人間以前」と「人間以後」をはっきり区別しなければならないこと。
つまり「自然地形」と「人為地形」を見わけ、その特性をわきまえることは、巨大都市に生きる人間としてきわめて重要なことなのです。
私の著作は、H・シュライバーの『道の文化史』を念頭に書いたものであったのだけれど、編集の方が私の文章を苦労して半分以下にパッチワークし、「絵」(ビジュアル)中心の本としてくださったのは痛し痒しで、
じっくり読んでいただければ、《文化史》の文脈はわかるはす。
表面だけみて「景観本」のレベルで云々する人がいるのは、残念というか心外。
まあ、本格的な『崖と坂の文化史』を書きなさい、ということなのかと思いますので、それを心して励みましょう。
その場合のタイトルは、『崖・坂・橋』ということになると思いますが―
標記のタイトルで、高校時代の先輩が拙著を購入した折の写真を送ってくれました。

東京は千代田区の神田神保町三省堂書店玄関正面。
江戸東京本のコーナーをもつ三省堂書店では、8月末にはすでに発売していたのですね。
しかし、入ってすぐの「ロイヤルボックスシート」とは驚いた。
いきなり、山本リンダになってしまう。
「困っちゃうな」。
岩窟王か、隠者のつぶやきを本にしたつもりなのに。
カラフルなコンピュータグラフィックスや写真画像に惑わされてはいけない。
私の本は、いま流行りの、街歩き本や、東京地形本などではないのです。
この本には、猛毒が仕掛けてある。
それが何かは、お買い求めいただいて、じっくり、すこしずつ、ご賞味いただければわかります。
じっくり読んだ人は、毒を取り込んで「賢く、強く」なれるでしょう。
すみません。
拙著の書店発売日は9月1日、明後日の土曜日でした。
何度も本屋さんに足を運んでいただいた方もいるようで、申しわけありません。
13ページの誤植は気になるものの、一見して売れそうな、カラフルで写真・画像の充満した本にはなっています。
実際、購入してじっくり目を通していただければ、見かけにくらべて、ずしりとした質量を感じられるはずです。
まあ、書いた本人がそう思っているだけなのかも知れませんが。
標記のタイトルで、拙著がようやく発刊されました(講談社、本体1800円)。奥付は2012年8月30日。
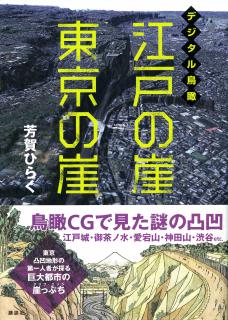
初刷りに誤植はつきものですが、出だしの部分でつまずいてしまったようです。
13ページ上段の4行目から5行目。
「だから前述の『地学事典』の見解では、江戸・東京に変動崖は存在しないことになる。」は、
「だから前述の『地学事典』の見解では、江戸・東京に崖は存在しないことになる。」としないと、意味が通じない。

もっとも基本的なところだから、どうしてこうなったかと自分でも理解に苦しむ。なにかと混線したのか。
他にも何ヶ所か、訂正すべきところはあるけれど、それは多分に表記上の問題で、たいした誤植ではありません。
しかし、出だしで理解不能だと、読者はそのあとつづけて読む場合は心理的に不安定になるでしょうね。
だから、とりあえず「誤植です」と、ここでアナウンスしておきます。