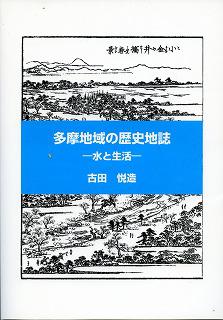客:句会やってるんだって?
主:主宰しているわけではないけど、世話係みたいなことをやって7年目かな。
客:飽きっぽい君にしては、よくつづくね。
主:さすがに最近は悩むよ。これでいいのかとね。
客:なんだい、それは。
主:うん。われわれのやっているのは結局「呑み屋句会」なんだけど、「新宿ゴールデン街の文壇バー」(ロバート・キャンベル)とも言われたところだから、発足時はそれなりの人たちがいたのね。つまり、短詩型文学というか、戦後俳句の到達点とまでは言わないけれど、ある程度の常識が、句会の場でなんとなく共有されていた。
けれどもいま若い人たちというか、「初心者」クラスが多くを占めるようになってしまうと、そうした前提が取り払われて、何でもあり。選句に困るものが多くなった。
客:いまの若い人たちは酒場で批判したり、議論しないから学べないんだろうな。それをやったらたちまち来なくなるだろう。批判しないで、誉められるものを誉めるだけにしたら?
主:うーん、それも難しい面がある。何といっても、若い人たちの句には「芸事俳句」とでも言うべき傾向があるからね。掛詞に走ってしまうなど、その典型なんだな。俳句は芸事の一種だと思っているらしい。
去年は学生に毎回授業(「表現と批評2」)の課題として俳句をつくらせてみたけど、最後まで5・7・5、17音ならべただけという結果におわった。それに較べれば、もちろん「作品」たらんと工夫して、一応「形」になっているけどね。
客:「芸事俳句」か。「うまいッ、座布団一枚ッ」だな。つまりは「型」の世界ね。たしかに誉めたらその「型芸」を誉めることにしかならないな。
主:人間存在の深淵から宇宙の極大までを表現するに至った現代俳句だが、その裾野は退嬰して季語を中心とした「盆栽芸」になりさがっている構図だね。
夏石番矢は「短詩型に託されるのが、日記風の季節感だけだとしたら、たいへんおそまつな話だ。季節感を突きぬけた世界観や宇宙観、あるいは人間観が問われない詩などは、滅亡すればよい」(『現代俳句キーワード辞典』1990)と言っていたが、その感をますます強くするよ。
客:俳句の「季語」というのは、近年テレビや雑誌、出版でも大流行の「日本すごい(スペシャル・万歳・美しい)」の淵源のひとつではないのかね。つまるところ、「ひとりよがり」の「日本イデオロギー」。それも決して江戸時代に遡るものではなく、高浜虚子あたり以降の根の浅いものだが。
思うに戸坂潤(『日本イデオロギー論』1936)も、過去のものと澄ましているわけにはいかないんじゃないかな。もちろん、竹内好(『日本イデオロギー』1952)もね。
主:うん。竹内は最近読み返して、「古典」であることを確認したよ。戦前であろうと戦後であろうと、「構図」の変わらないところが「日本」なのね。
客:いや、構図だけは格段に深く、大きくなったよ。「アウシュヴィッツ以後、詩を書くことは野蛮である」(アドルノ)という言葉があるけれど、われわれは「3・11以後、季節や自然をうたうのは野蛮である」というべきなんだ。
「国破れて山河あり」は遠い過去。S・アレクシエービッチの「あの時から、世界はまったく変わったのです」(『チェルノブイリの祈り』)は、現在を生きるすべての人間、いや生物についてあてはまるのだからね。
主:世界は、ひとりよがり「季語」や「日本」を置いてきぼりにして異次元に突き進んだのね。そのことに鈍感なのか、あるいは耳目をふさいでいるのか。俳句にかぎらないけれど、「日記風の季節感」やエピソード、ないしは絵空事を仕立てて見せるのは、もう勘弁してもらいたいな。
客:そう露骨にも言えないだろうから、まずは阿部筲人の『俳句 四合目からの出発』(講談社学術文庫)あたりを薦めて、「日本語月並み表現の恐るべき均一性」を、警告してみたらどうかね。
主:それもいいかな。
テレビ番組や出版を契機とした「地形ブーム」というのがいいまだ健在らしい。
しかしその多くは東京を中心とした巨大都市圏に住む者のひまつぶしないしはマニアックな所業の延長であって、私の関与するところではない。
拙著『江戸の崖 東京の崖』が代表だが、その主張は「地形マニア」の「さまざまな意匠」とは隔絶しているのである。
東京というよりも、日本列島上の「首都圏」は、その存在自体が「崖」であり、「奇形」である、というのがその主張である。
そうして、現在は「江戸時代」につづく「東京時代」であって、その「東京時代」(東京国家)を「止揚」しなければ、われわれの未来はありえない、というのが究極の主張である。すなわち、われわれが生き残る道は、「都」も、「東京」も、廃棄することにしか存在しないのである。
地表上きわめて特殊な、4枚のプレート(岩盤)のせめぎあう「新規造山帯」に位置する日本列島において、「巨大災害」は地表上これまたきわめて特殊な人口集中地域(首都圏)に必然的に生起する、不可避な現象である。災害の規模は、人口の集中規模と「都市化」の度合に比例して昂進するからである。
人間が「地形」を考察するには、「人間の土地」から「人間」を切り離し、そうして再度「人間と地形」の現在を対象化しなければならない。
こうした規定性に目を向けない、どうでもいいような「景観論議」(その多くは建築系の構造論者およびそれに追随するおっちょこちょいやノー天気派、そしてタレントであるが)、マニアックな知ったかぶりは、すべて無効である。
ところで、大学の新聞会といえば、硬派学生の代表格のようなものだったが、過去と現在は隔絶しているらしい。
しかしその新聞会から取材があって、私の話が『THYME』(東京経済大学新聞会)という雑誌に掲載された。
以下は学生の聞き書きだが、それはそれでよいと思っている。

写真を撮るために、三ノ輪からいまや希少な存在となった路面電車に乗って、荒川区立「あらかわ遊園」まで杖を曳いた。
都電の荒川遊園地前停留所の安全地帯は、保育園か幼稚園の子どもたちでいっぱいだった。
午後4時近くだから、遊園地から帰るところだったのだろう。
撮影対象は、荒川区の「永久水利」施設。
「永久水利」とは、震災などで上水(水道)が利用できない事態に備えた試みのひとつで、隅田川そのものを水源とするための名付けなのだろう。しかし河川水といえども無限ではない。「悠久の自然」は幻想である。地球表面上、変動著しい日本列島においてはなおさらである。

あらかわ遊園スポーツハウス前の説明板
「水利」とは言うものの隅田川の水は、飲用はむろんのこと洗濯、掃除にさえ使える代物ではない。
いかに「処理」されたとしても、そこを流れる水の「雨水と処理希釈された下水の混合水」という本質は変わらない。
ごく一部を除き、都内の都市河川で釣った魚を食べることは不可能である。処理下水臭がきついのである。
だから説明板にあるように、水利とは消防(消火)水利以外ではありえない。しかし木造住宅密集地域を抱えている区にとっては、永久にも見えるありがたい水源なのだろう。
願わくは、肝心の折に川水を汲み上げるポンプの電源がない、といった事態が起こらざることを。

園内の「みずあそび広場」の水流。一見するときれいそうだがよくみると処理下水特有の泡が浮いて流れる。隅田川からポンプアップされた水である。この水流と「永久水利」の関係を問い合わせたが、皆知らなかった
ところで、園内で小学校4年生くらいの男の子が「潮(しお)の匂いがする」と言っていたのには驚いた。
そこに漂うのは、神田川でも隅田川でも多摩川でもおなじみの、下水処理薬品の臭いが主体の「現代都市河川臭」にすぎなかったからである。
プールで泳ぐのがせいぜいの子どもたちは、海の匂いと都市河川の処理下水臭を区別できないのだ。
あるいは大人たちでも「無分別感覚」者が多数派となりつつあるのだろう。まがいものの河川水、まがいものの香りが充満している巨大都市に住む、あるいはそこで育つ不幸を思う。
水処理化学を専攻している人ならば、こうした「都市河川臭」の正体はすぐにわかるのだろうが。

一般に処理下水は、ところどころにこのような「泡溜まり」をつくりだす。「親水公園」など、処理下水応用「清流」施設ではちょっと気をつければどこにでも目にし得る光景である。この泡の正体も明らかにしたいところだ
セーヌ川は最近トライアスロンのコースに利用されることがあるという。
東京23区や多摩東部では考えられないことである。
水泳競技が可能とすれば、隅田川とは比較にならないほどきれいだということである。
それが下水処理技術や処理基準の差にあるのか、(雨水と汚水の)合流式と分流式の違いであるのか、いまのところわからない。
あるいは流域都市人口と工場数の規模、ないしはアジア的密集とヨーロッパ的分散の差異も関与しているかもしれない。
いずれにせよこのようなところにこそ、都市の本質的課題は存在する。
この根本課題の諸元が明らかになって(一般に共有された情報になって)いないとすれば、東京の未来は明るくないというべきだろう。
「ニッポンすごい」「トーキョー世界一」の、はるか手前の課題だからである。
100万都市江戸の隅田川以西を支えたのは、多摩地域の水源(神田上水・玉川上水)であった。それは井戸水すら涵養した。
その時代、下水は汚水ではなかった。
だから隅田川以東、埋立造成地である深川エリアの飲み水は、荒川(隅田川)の比較的上流から汲んで来た水売りの水にたよることができたのである。

隅田川とあらかわ遊園への河川水汲み上げ場所附近。奥に見えるのは小台橋
昨年12月の6日に、仙台第二の地下鉄東西線が開通したこともあって、3・11から5年目の春、市内を歩き回った。
東西線の東のターミナル駅は荒井駅で、津波が全面積の56パーセントに侵入した若林区のほぼ中央、荒井東に位置し、地上3階地下1階の駅舎の1階部分は「せんだい3・11メモリアル交流館」があり、2階では被災関連の展示が行われていた。
仙台平野のどまんなか、沖積地であるから、このあたりに当然「坂」は存在しない。
津波からの逃げ場も、自然地形としては存在しないのだ。
しかし今回はじめて判然としたのは、村田町から仙台市を経て利府町に延びる長さ20キロ以上の活断層帯「長町-利府断層」の断層崖が、仙台市街の沖積地と段丘エリアの空間上の境界線で、同時に時間的な画線でもあったということである。
江戸初期に行われた山城仙台城の整備と、上水(四ツ谷用水)敷設による台地上への城下町建設以降、この長町-利府断層崖から西側の台地が「仙台史」の主舞台に転じた。
つまり、弥生時代から中世までの仙台の歴史は、断層崖東側の沖積地に展開していたのである。
藤原氏が整備したという東大道につながる「東(あづま)街道」は断層線に沿い、その直下を北上して多賀城を目指した。多賀城以前の陸奥国府は東北本線長町駅と太子堂駅の東、広瀬川との間の郡山に存在したし、「陸奥国分寺」「陸奥国分尼寺」も東街道に接してその東である。
陸奥エリア屈指の前方後円墳「遠見塚古墳」や「雷神山古墳」も沖積地に造営された。
今や100万人都市仙台の歓楽街として知られる「国分町」だが、そこに名をとどめる国分氏の本拠地もまた、今日の若林区役所から陸奥国分寺のエリアにあった。国分氏は、陸奥国分寺から姓を仮借したのである。
かくのごとく中世までの仙台の中心地は、地下鉄東西線「連坊」駅以東であった。
征服者は船を用い海から仙台平野に侵入して橋頭堡を築いたのであろうし、また近世の用水以前、台地部に水の便はなかったのである。
仙台平野の歴史を2000年前から追えば、当初の1600年は活断層の東側の沖積地に展開し、最近の400年ほどがその西側を舞台としたわけだ。
よく1100年ほど前の貞観地震が引き合いに出されたが、地質調査によればこのエリアに5年前と同じような規模の大津波が来襲したのは約2000年前の弥生時代だという。
その後一旦は人間の居住跡は途絶えるものの、数百年後の古墳時代には人が集中しはじめる。
人間とは、記憶するとともに忘れもする動物であり、忘れるがゆえに生きていくかなしい動物でもあった。

図の中央「仙台穀町郵便局」の下に「石名坂」と町名がある。長町―利府断層崖は図の右上の「連坊」(地下鉄駅の記号はあるが路線ルートは描かれていない)から左下「地下鉄南北線」の「線」の文字にかかって、影の表現で示される。
仙台市のサイト(http://www.city.sendai.jp/wakabayashi/c/miryoku_monoshiri.html#330)には「仙台七坂」として、「仙台は河岸段丘の上につくられているだけに、変化に富んだ地形があちらこちらで見られる。坂道が多いのも特徴の一つで、城下を代表する7つの坂は「仙台七坂」として呼びならわされてきた。いまなお、使われている坂の名もある」の説明があり、以下そのひとつひとつ(大坂、扇坂、藤ヶ坂、新坂、元貞坂、茂市ヶ坂、石名坂)に簡略な説明をしているが、この断層崖について言及はない。
留意すべきは、仙台七坂のほかの6坂はすべて段丘エリアに存在するのに対し、唯一「石名坂」だけがこの断層崖にかかる坂、つまり段丘面と沖積地をブリッジする位置にあって、しかもそれは線状の坂の名というより一定の広がりを持った「町名」である、という点である。
また「石名」(石那)が仙台出身元吉原の花魁名に由来するという伝承も、この坂が江戸初期ないし江戸以前にかかるものであることを暗示する。

仙台市若林区石名坂61にある円福寺境内の石名大夫墓
つまり今では南北の道筋とされる石名坂だが、古くは道が南北東西に交差する+字の坂(東側と南側が低い)であった可能性を否定できないのである。
繰り返せば、仙台七坂のうちほかの六坂は段丘崖にかかり、石名坂のみが断層崖にかかる。
その断層崖は2000年の仙台平野の歴史を二分する界線であった。
したがって、仙台七坂のうち石名坂こそ最古の坂(要路の急傾斜部で、命名され、緩傾斜とされた部分)である、という推論が成り立つのである。
仙台地下鉄南北線が開業したのは1987年、それに交差する東西線は約30年後ミニ地下鉄にスケールダウンしてようやく開通した。
もちろんグーグルマップに南北線のルートは線引きされている。
しかし東西線のそれは、開通4ヶ月を過ぎようとしている今日でも、依然として描かれてはいない。
知識や記述のたぐいは、往々にしてちぐはぐで偏頗なものなのである。
「石名坂」という坂は、藤沢にも日立にも所在する。坂名由来の詮索は、伝説とは別のところに求めなければならない。
16年前の4月末に発売された福山雅治のCD「桜坂」は200万枚を超す大ヒットとなったという。
この2月27日、大田区南久が原の昭和のくらし博物館で、「崖・水・くらし ―建築以前のこと」と題して2時間ほど話をしたが、それまで桜坂という坂も知らなければ、福山雅治という名前も、ましてその曲も聴いたことはなかった。
下見で大田区の国分寺崖線地域を歩いていて、結局「桜坂」と「ぬめり坂」に話の焦点をしぼることにして、はじめて十数年前の社会現象を知ったわけだ。
一般的な説明では、国分寺崖線は田園調布あたりまでつづくとされるが、国分寺崖線を「立川段丘の後面段丘崖」(松田磐余)と定義すると、国分寺崖線は大田区鵜の木一丁目の光明寺下までたどることができる。桜坂は中原街道の一部で、国分寺崖線を上下する傾斜部にあたる。
道端に立てられた説明板には、「桜坂 (さくらざか)/ この坂道は,旧中原街道の切り通しで,昔は沼部大坂といい,勾配のきつい坂で荷車の通行などは大変であったという。今ではゆるい傾斜となっているが,坂の両側に旧中原街道のおもかげを残している。坂名は両側に植えられた桜に因む。/昭和五十九年三月大田区」とある。
wikipadiaでもほぼ同様の説明をしているが、実は「桜坂」と「沼部の大坂」とは、空間的にも時間的にも別個のものなのである。

上の画像の2つのブックマーク(ピン)の間が現在の桜坂にあたる部分で、明治期までは平坦な段丘面であった(「東京時層地図」から)
沼部の大坂は丸子の渡しにつづく中原街道の要衝だが、国分寺崖線を開析した小規模な谷の壁をたどる坂道で、私の「坂の5類型」でいえば基本的には第3類型の「谷道坂」にあたり、第4類型の切通坂ではない。

いまや桜坂の象徴のような「赤い橋」も、かつて中原街道の平坦面でそれに交差していた道が切り通しによって分断されたため、その「補償」として戦後に架けられたもの。観光が意識されたわけもない。
「坂の両側に旧中原街道のおもかげを残している」いわば「両脇の急坂」も、新たな切り通し坂による「地域分断への補償」として造作されたのであって、「中原街道の旧道の様子を残しているのは、区内ではこの付近だけである」という「大田区文化財 旧中原街道」の説明板も、ただし書きが必要であろう。
日程 2016年3月27日(日曜日) 午前の部&午後の部
集合 午前の部:10時 国分寺駅改札前
午後の部: 2時 国分寺駅改札前
案内人 芳賀ひらく
コース予定(一部変更可能性あり)
午前の部:国分寺駅北口→野川源流(日立中央研究所南)→伝村上春樹洋子夫妻旧居跡→姿見の池・畠山重忠と遊女夙妻(あさづま)太夫伝説の地→東福寺傾城の墓→鎌倉街道跡→古代官道跡→都立武蔵国分寺公園→国分寺崖線→真姿の池湧水群・真姿の池(玉造小町伝説)→お鷹の道→野川不動橋→池の坂→国分寺駅南口
*昼食は国分寺駅周辺で、各自*
午後の部:国分寺駅南口→都立殿ヶ谷戸庭園→村上春樹・ピーターキャット跡→新次郎池→貫井弁天→野川河川敷→滄浪泉園→質屋坂→小金井小次郎墓→はけの道→はけの森美術館【喫茶部休憩】→大岡昇平『武蔵野夫人』故地富永邸→ムジナ坂→都立武蔵野公園→二枚橋→都立野川公園→多磨霊園北口→【バス】武蔵小金井駅
参加費 500円(資料代 資料:旧版地形図・記録/文学作品抄)
午後の部・午前の部通し参加可(参加費は通しでも500円)
限定20人・要事前申込 問合せ・申込:hiraku@collegio.jp
当日連絡 080-6554-3805(多少の雨天でも行います)
*保険などの用意はありません。事故がないように。万一の場合は基本的に各自で対応をお願いします。
*午後の部終了後、武蔵小金井周辺で春夕小宴予定。
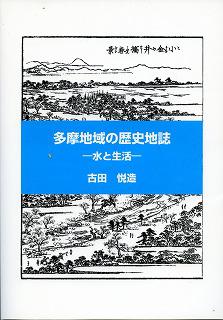
古田悦造著 『多摩地域の歴史地誌 -水と生活―』
ISBN978-4-902695-28-1 C3025
A5判 120ページ 本体1800円+税
「江戸の水元」にして
今なお巨大都市水源の一端を担う多摩
その水とヒトの生活の実際を、歴史地理学
の手法で概観する待望の著
湧水や小河川利用から井戸水、そして用水利用、
さらに近代水道の導入と一元化の現状までをたどる。
地図・図版・写真多数、参考文献・索引付
古田悦造(ふるたえつぞう)
1950年、名古屋市生まれ。1980年筑波大学大学院単位取得満期退学。1980年東京学芸大学着任。1987年文学博士(筑波大学)取得。2001年東京学芸大学連合大学院担当。2016年東京学芸大学退職。/単著『近世魚肥流通の地域的展開』、共編『歴史地理調査ハンドブック』『地誌学概論』、論文「『武蔵野夫人』の地理学的一考察―水系を中心に」「武蔵国多摩郡小川新田における開発目的の時代差」ほか
目 次
はしがき/第Ⅰ章 はじめに-歴史地誌学の考え方-/第Ⅱ章 湧水・小河川利用の生活/第Ⅲ章 井戸水利用の生活/第Ⅳ章 用水利用と生活/第Ⅴ章 水道利用と生活/あとがき/索引
表目次
Ⅱ-1 多摩郡の村落における湧水・清水の状況/Ⅱ-2 多摩郡における古城・館趾/Ⅲ-1 青梅市新町における『仁君開村記』に基づく井戸の記述/Ⅳ-1 武蔵国における郡別石高の推移/Ⅳ-2 玉川上水の多摩地域における分水の状況(開設年次順)/Ⅳ-3 小川村(旧小川新田)と小川新田との比較/Ⅳ-4 小川村(旧小川新田)と小川新田の成立目的/Ⅴ-1 東京都における浄水場の状況/Ⅴ-2 多摩地域における水道事業の変遷過程/Ⅴ-3 多摩地域の近代水道と都営一元化/Ⅴ-4 多摩郡における水利・用水の状況
図・写真目次
Ⅰ-1 系統地理学の考え方の概念図/Ⅰ-2 地誌学の考え方の概念図/Ⅰ-3 動態地誌学の考え方の概念図/Ⅰ-4 歴史地誌学の考え方の概念図/Ⅱ-1 東京の地形分類/Ⅱ-2 多摩地域における地形断面の概念図/Ⅱ-3 東京における湧水57選/Ⅱ-4 入間郡堀兼の井の挿絵/Ⅱ-5 2つの湧水タイプ/Ⅱ-6 井の頭池の景観/Ⅱ-7 現在の井の頭池の湧水地点/Ⅱ-8 武蔵野地域における主要な湧水地/Ⅱ-9 湧水地と標高との関係/Ⅱ-10 ママ下湧水群の湧水地点の一例/図Ⅱ-11 ママ下湧水の小河川/Ⅱ-12 滄浪浪泉園内の湧水地/Ⅱ-13 殿ヶ谷戸公園内の湧水地/Ⅱ-14 貫井神社境内の湧水/Ⅱ-15 お鷹の道に沿う小河川での湧水利用/図Ⅱ-16 深大寺の湧水と景観① /Ⅱ-17 深大寺の湧水と景観②/図Ⅱ-18 武蔵国分寺の景観/Ⅱ-19 武蔵国分寺の挿絵にみられる古瓦/図Ⅱ-20 武蔵国分寺の文字瓦(郡名)/図Ⅱ-21 河岸段丘に沿ってみられる遺跡分布/Ⅱ-22 八王子城趾を中心とした元八王子村の全景/図Ⅱ-23 八王子城趾の挿絵/図Ⅱ-24 滝山城趾の挿絵//図Ⅱ-25 滝山城の縄張/図Ⅱ-26 片倉城の縄張/Ⅱ-27 片倉城趾の挿絵/図Ⅱ-28 深大寺城の挿絵/Ⅲ-1 羽村市の「まいまいず井戸」の景観/Ⅲ-2 青梅市の「大井戸」の景観/Ⅲ-3 青梅市の「大井戸」の復原平面図/Ⅲ-4 青梅市の「大井戸」の断面図/Ⅲ-5 青梅市「大井戸」の主体部(発掘調査時)/Ⅲ-6 青梅市新町に現存する吉野家の井戸/Ⅲ-7 あきる野市淵上の「石積み井戸」/Ⅲ-8 昭島市における井戸の分布//Ⅲ-9 昭島市「おねいの井戸」の地形断面図/Ⅲ-10 青梅市「親井戸」の地形断面図/Ⅲ-11 武蔵国庁推定地周辺における古代の竪穴住居址の分布/Ⅲ-12 府中市および調布市で発掘された井戸の平面図および断面図/Ⅳ-1 『武蔵名勝図会』にみられる府中用水/Ⅳ-2 玉川上水の分水路/Ⅳ-3 多摩地域における新田集落の分布/Ⅳ-4 小川村(初期新田)の村絵図(延宝2<1674>年ごろ)/Ⅳ-5 多摩郡上成木村における石灰生産の様相/Ⅳ-6 小平市上宿の景観/Ⅳ-7 小川新田(中期新田)の村絵図/Ⅳ-8 小川村(初期新田)の母村である岸村の位置/Ⅴ-1 東京都における水源量の推移/Ⅴ-2 東京都の水道水源と水道関係施設の分布/Ⅴ-3 東京都における水道非一元化地域
「代々木九十九谷凹凸地形徹底踏査」
日時:2016年2月13日(土曜日)午後2時集合
集合場所:京王線初台駅・東改札を出たところ(地下)
コース概要:京王線初台駅から小田急線代々木上原駅まで、約2時間半
尾根道の用水路跡と7つの谷・井戸と湧水と
参加費(資料代)1000円
年末に女房のツテで、初期ユダヤ教研究で世界的に知られる土岐健治先生にお目にかかることができた。
先生のお宅のお庭には苗から植えたばかりのイチジクが実を付けていて、その2、3個が食卓にのぼった。
イチジクが実をつけるところはエデン(楽園)であると、先生は笑っておられた。
「知恵」を得たアダムとイブの恥部を隠したのは、聖書の創世記にはじめて植物種名が登場するイチジクである。
先生にお会いするのは躊躇があった。
私は前の会社で『死海文書の謎』などという翻訳本を出して、それなりの利益を得たものだから恥じ入るのである。
四半世紀も経たからすでに時効かもしれないが。
私の故郷は、自然主義文学の初期作品として知られる、真山青果の「南小泉」の地である。
その冒頭には、この地は卑湿のためイチジクがよく生える、とあった。
そこは別にエデンでもなかったが、いろいろな意味で心情の原景をかたちづくった場所である。
現在では、昨年末に開通した仙台市営地下鉄東西線沿線から外れた、場末に近い市街地である。
しかしそこは、私の記憶のなかでは、エデンである。
ただ、ここで言いたいのは、イチジクとその生える場所のことではなく、カミサマのことである。
「年末はサンタクロース。明ければ神様」という、いわば現代日本人の生活パターンが、「われわれ」のカミサマの原姿を映しているように思われるのである。
サンタクロースは、お父さんであり、お母さんであり、ジジババで、つまりは「人間」である。
現代の神社は、年始にそのほとんどを懸ける、地域産業のひとつである。
「カミ」(カン)とは、おそらく古墳時代には、部族国家の首長の称だったのである。
その部族国家連合の盟主は「オオクニヌシ」である。
「神無月」とは、部族国家首長会議の謂である。
それぞれのクニノミコトは、年に一度出雲に集合したのである。
そうして「カミ」とは、元来上位者の称であった。
だから「God」とは懸隔がありすぎるのである。
大陸から海路瀬戸内海を東進し、奈良盆地を中心に勢力を展開し、中央集権国家を形成するのは後発の部族である。
「god」と「カミ」を短絡してはいけない。
日本語の「カミ」は決して万能唯一の「神」ではない。
しかし日本列島上の「神=上=官」の意識構造は、今日の《「官」にブラ下がる「民」》という「ドレイ構造」の基本である。
それは「国立競技場問題」にまで貫徹しているのである。

東京経済大学第1研究センターの研究室から撮った、
晩秋の日の出ならぬ日没。
中央右下に富士山の稜線がみえるのですが、わかるでしょうか。
(2段階拡大してみてください)
ここは「国分寺崖線」の真上に位置していて、下れば湧水地(新次郎池)、
初夏には窓がクヌギの黄色い花房で縁取られ、蝶などの昆虫が集まります。
ことしもよろしくお願いいたします
2016年1月1日