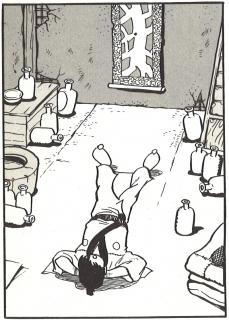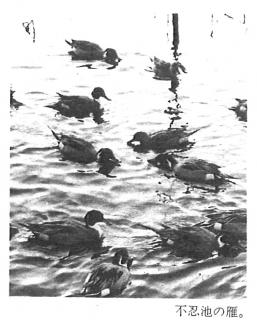5月 29th, 2022
「地図文学傑作選」 その13
本項の手仕舞いにあたっては、短歌と俳句作品から目についたものを掲げることにする。
短歌と地図ということになると、石川啄木の次の作品がすぐに思い浮かぶだろう。
「地図の上朝鮮国にくろぐろと墨を塗りつつ秋風を聴く」
言うまでもなく1910年8月の日本による韓国併合を詠じたもので、自国領を中心に置きそれを赤く塗る近代地図の一般原則を裏返し、「亡国」の印として朝鮮半島部に墨汁塗布したのである。日清日露両戦争後ナショナリズムに浸った日本人のなかでも、啄木の特異な位相がうかがわれる。
もちろんその2月前には大逆事件と俗称される幸徳秋水らの逮捕があり、処刑は翌年1月とはいえ「時代閉塞の現状」は頂点に達していた。啄木が現在の文京区小石川の寓居で26歳の生涯を閉じるのは1912年の4月であった。
併合前の韓国の国号は「大韓帝国」であるが「併合条件の綱要」において、明の洪武帝から下賜された「朝鮮」の呼称が復活された。「くろぐろと」否定されたのはその呼称でもあった。なお「大韓帝国」の「帝国」とは、領土にかかわるというよりは自前で暦がつくれることを意味したという。
時代は大分とぶが、1985年に78歳で亡くなった「幻視の女王」葛原妙子の「地図」の語を含む歌は次のごとくである。
「黒峠とふ峠ありにし あるひは日本の地図にはあらぬ」
二句目と三句目の間を一字空け、三句目を字余りとした破調である。
「或いは」を「あるひは」と書くのは歴史的仮名遣いとしては誤用とされるが、それを承知で意図的になされた節がみえる。つまりこの歌のテーマは「異界」へのpass(越境点=峠)であり、「地図」とはそれを記載した図である。日本であろうと外国であろうと、幻視者にとって異界への分水界はどこにでも存在しうるが、それは視ようとして見えるものではない。作者にとって黒峠という言葉は、その言葉だけが頭の中で不意に出現したのである。だから「あるひは」なのである。
今日「黒峠」と入力すれば、Google Mapはただちに島根県との境に近い広島県山形郡安芸太田町横川の内黒峠を指し示す。一方Black Passでは世界地図のどこにも該当しないようである。つまり「黒峠」という地名は現実にはどこにも所在しない。
葛原のもっとも代表的な歌として「他界より眺めてあらばしづかなる的となるべきゆふぐれの水」がある。それと同作「高きよりみし白昼に人群は大いなる魔のごとくながるる」を並置してみると、地図の原理である「視座の転位」が顕著であることがわかる。すくなくとも古代においては、地図とは一種の「空間幻視」の賜物でもあったのである。
より直接的な空間幻視の歌は、北原白秋の
「大きなる手があらはれて昼深し上から卵をつかみけるかも」
であろう。
若山牧水の
「幾山河越えさり行かば寂しさの終(は)てなむ国ぞ今日も旅ゆく」
は幻視ではなく平明な旅情歌だが、その視点はやはり上空にあり、地図的であることに変りはない。
地上視点であるが、古代の「国見」のごとく崖上(現在の東京は千代田区の駿河台男坂上)から見下ろした巨大都市を、近代詩のかたちで「野の獅子の死」にたとえたのは上京した石川啄木(「眠れる都」、『あこがれ』所収)で、1904年11月21日のことであった。
これらに対して地図現物が登場するのは、天台宗僧侶にして歌人および詩人、というよりも日本野鳥の会の創立者として知られる中西悟堂の次の歌である。
「槍ヶ岳のいただきに来て見放(さ)くるは陸測二十万図九枚の山山」(「安達太良」)
いわば「山頂歌」であるが、ただちに思い出されるのは斎藤茂吉の
「陸奥(みちのく)をふたわけざまに聳(そび)えたまふ蔵王の山の雲の中に立つ」(「白桃」)
であろう。こちらには地図の名は登場しないが、奥羽山脈の分水嶺が足元に踏まえられ、歌の構図が地図である。しかしここで注意すべきは「陸奥」(みちのく)の語がつかわれている点である。蔵王は現在の宮城県と山形県にまたがる山塊であるから、ただしくは陸奥と出羽すなわち奥羽でなければならない。山形県は現在の上山市出身の茂吉にこの語遣いをさせたのは、「みちのく」が「東北」に対応する語として逆にイメージされるようになっていたからであろう。「東北」は明治初期に方位称から地域称として転用された新語で、歴史的経緯から言えば「差別語」である。したがって「東北学」は、すくなくとも明治以降の時間幅にしか該当しえないのである。こうしたことに無関心ないし無神経な言説は学問とは言えない。
ところで悟堂歌にある「陸測二十万図」といえば、日本近代文学の白眉のひとつでもある泉鏡花の代表作『高野聖』(1900年)の冒頭次のように登場するのである。
「参謀本部編纂の地図をまた繰開(くりひら)いて見るでもなかろう、と思ったけれども、余りの道じゃから、手を触るさえ暑くるしい、旅の法衣(ころも)の袖をかかげて、表紙を附けた折本になってるのを引張り出した。/飛騨から信州へ越える深山(みやま)の間道で、ちょうど立休らおうという一本の樹立(こだち)も無い、右も左も山ばかりじゃ、手を伸ばすと達(とど)きそうな峰があると、その峰へ峰が乗り、巓(いただき)が被(かぶ)さって、飛ぶ鳥も見えず、雲の形も見えぬ。/道と空との間にただ一人我ばかり、およそ正午と覚しい極熱(ごくねつ)の太陽の色も白いほどに冴え返った光線を、深々と戴いた一重の檜笠に凌(しの)いで、こう図面を見た。」
「参謀本部編纂の地図」とあるからには、少し地図に詳しい向きは旧陸地測量部「誉の五万」、つまり5万分の1の地形図と思うかも知れないが、さにあらず。こうした内陸の地にあっては当時は5万や2万分の1(2万5千分の1図ではなく、当初の迅速ないし仮成および正式2万分1図のこと)図はおろか、伊能図すら作成されてはおらず、資料を搔き集めはじめての日本列島142面が整備されたのは1893年。それがこの「参謀本部編纂の地図」すなわち「輯製二十万分一」図であった。この件についてはかつて一文を草したことがあるので、詳しくはそちらを参照されたい(「峠と分水界」,『地図中心』2012年6月)。
茂吉歌のほかに、「地図」の語を使わず地図的なイメージを示した歌として
「切り傷は直線をなすアフリカの幾つもの国境(くにざかひ)にも似て」(山田航)
がある。現役歌人の歌である。
アフリカの「傷跡」国境はもちろんヨーロッパ植民地政策の結果だが、そのもっとも古くまた長大な「傷跡」は、アフリカではなく南アメリカのブラジル国境である。南アメリカではブラジルだけがポルトガル語を公用語とし、他はスペイン語なのである。これは15世紀末から16世紀にかけて、ポルトガルとスペインが「新大陸」の領土獲得を争っていた時分のローマ法王裁定「世界分割線」(Meridian Demarcation)の名残りである。分割線より西側に不定形に突き出した部分は、その後アマゾン川をさかのぼって領域をひろめたポルトガル人の足跡を示している。直線でない「国境」も地表の傷跡には違いないのである。
さて、俳句にあらわれた地図としては
「大白鳥地図のあちこち消してくる」(杉野一博)
がまず一押しであろう。
大型の渡り鳥のゆっくりとしつつも力強い羽ばたきの動きが目に見えるようで、それを「地図を消」すと表現したのは、国境や軍事境界線そしてヒトがつくった構造物の類を眼下にパスしてほぼ一直線に飛んでくるからである。それが「あちこち」とはいくつかの群れが同時に飛翔してくることを示す。越冬に適した湿地や水辺が極端に減少した今日、それはかつて存在した幻想的な渡りの光景なのである。
一方で
「寄生虫己れの地図を持っており」(山本桂子)
は「地図認知」の始原を直截に表現して比類ない。無季であるが、地図そのものにも一般的には季節は存在せず、強いて言えば「通季」である。いかなる動物も場所を認知するそれぞれの能力を備え、各自の環境世界(ユクスキュルでは「環世界」)に生きる。「ミミズだって、オケラだって、・・・」(やなせたかし「手のひらを太陽に」)なのである。
「月と眠る/地図の一点に横たわり」(江里昭彦)
も、「地図」を使って秀抜である。そこには月に照らされて眠っている自分を見下ろしている、もう一人の自分がいる。「月」は秋の季語とされている。先の杉野の作品に「箱庭を出る足取りの確かなり」という作もあって(「箱庭」は季語としては夏とされる)、こうした句作の背景にスケールアップ、スケールダウンという、ベクトル向きの反対な想像力の動きが潜んでいることを垣間見させる。スケール移動は地図の構造原理のひとつである。
「地図」の語を使わず地図的なスケール移動を示した端的な例は
「渡り鳥みるみるわれの小さくなり」(上田五千石)
である。
俳句の季語すなわち歳時記や季寄せの分類では、「渡り鳥」や「鳥渡る」は秋、「鳥帰る」「鳥雲に」は春とする。ただし「燕帰る」逆に秋となる。「渡り鳥」には夏鳥もいれば冬鳥もいるから、それだけでは季節は弁別できないはずだが、歳時記では無理やり秋とするのである。
「みるみるわれの小さくなり」には、飛び去る鳥と地上に取り残された自分と、二つの視点つまり二人の自分が同時に存在する。
「渡り鳥」を季語の制約から外してみると、遠ざかる鳥の群れは何千キロも離れた繁殖地に戻る姿にほかならず、季節は春である。
しかし作者は「『渡り鳥』が『みるみる』うちに『小さくな』って秋空のかなたへ遠ざかって行ったのが事実」で、「それをみつめて立っている自分が『みるみる小さくな』っていくように感じられたのは真実」という。そうであれば、鳥たちは最終越冬地の少し手前で休憩していただけなのだから、北に帰る姿よりも景としてはずっと小規模、短詩としての感動も小粒なのである。
つまりこの句の「妙味」は、遠ざかる鳥を見ていた作者の頭のなかで「視座の転位」が一瞬のうちに自動的に起動した、というその一点にかかるのである。
季語の有無、季感の矛盾にかかわらず、これらの句は視座の転位と「Cosmic View」的な漸移のスケール移動を併せ持つ最短の「地図文学」といっていい。
ただし『日本の俳句はなぜ世界文学なのか』(ドナルド・キーン/ツベタナ・クリステワ、2014年)というタイトルの本があるにもかかわらず、「渡り鳥」や「月」「箱庭」「祭り」「踊り」等々に代表される「ひとりよがり季語」に依存するかぎり、「俳句」は「世界文学」はおろか奇形にしてお家芸の「島国文学」に甘んじるのである。